「スーダンは現在、記録上最大の人道危機であり、世界最大かつ最速で増加している避難危機である」。2024年12月、国際NGOである国際救済委員会(IRC)がこのように発表した。2023年4月、同国で勃発した紛争が原因で1,460万人が避難しており、人口の64%以上に値する3,040万人が緊急支援を必要としているという。死者の数はまだ明らかになっていないが、ハルツーム州だけで61,202人が亡くなったという報告もある。
しかし日本の大手報道機関がスーダンの紛争及び人道危機を大きく取り上げているとは言い難い。例えば、読売新聞の報道量を計ってみると、2025年1月にアメリカのロサンゼルスで発生した山火事に関する3日間の報道量だけで、スーダンに関する1年分(2024年)の報道量を上回った。また同紙は、2024年に英国王室の2人のがんについて、スーダンの状況より2倍も多い報道を行った(※1)。
2024年、日本のメディアの視線はこの世界最大の人道危機ではなく、イスラエル・パレスチナとロシア・ウクライナに集中していた。スーダン以外にも、「人道報道」の対象にならなかった「人道危機」は数多くある。今回の記事ではこの観点から報道における格差を探る。なお、「武力紛争にみる日本の人道報道を問う」と題されたGNVの過去の記事(2022年3月31日)も参照いただきたい。

戦火にまみれたスーダンのアムドゥルマン市場(写真: Abd_Almohimen_Sayed / Shutterstock.com)
「二つの大きな戦争」
世界各地の人道危機の規模を把握するには、IRCが毎年発表している10大人道危機のランキングがひとつの目安になる。2024年は1位から10位まで、スーダン、パレスチナ占領地区(以下パレスチナ)、南スーダン、ブルキナファソ、ミャンマー、マリ、ソマリア、ニジェール、エチオピア、コンゴ民主共和国という順であった。これらの国々には100万人単位で食糧不足に陥っている人、避難民になっている人などが存在しており、膨大な人道支援が必要とされている。このリストに載っている国のいずれもが武力紛争を抱えている。
しかし、2024年、日本のメディアはこれらの人道危機のうち大半をほとんど取り上げなかった。2位のイスラエル・パレスチナと10位にランクインしなかったロシア・ウクライナが紛争に関する注目を独占しており、他の紛争がメディアの視野に入ることは稀だといっても過言ではない。例えば、毎日新聞は社説(2024年3月27日)で「世界は、二つの大きな戦争のさなかにある」と主張した。イスラエル・パレスチナとロシア・ウクライナを指しているこの文言をみる限り、スーダンは「大きな戦争」として捉えられていないようだ。
2024年の1年分の報道量(※2)をみると、この傾向が明らかとなる。以下のグラフが示すように、この「二つの戦争」に関する報道量だけ突出しており、他の紛争とは比較にならないほどの大きな差がついている。10大人道危機のうちの7つに関しては、それぞれの危機を対象にしている記事がゼロ、もしくはゼロに近い数字となっている。スーダンは平均して月に約1件の記事が掲載される程度の報道量にとどまっている。ガザとウクライナ以外に本格的と言えるほど報道量が確認できるのはミャンマーのみである。
これほどの膨大な報道格差が生じている背景には様々な要因が考えられる。その中では、自国の国益や政治的関心が占めるウェイトが大きいだろう。例えば、ロシア・ウクライナ紛争に関しては、核兵器を保有する大国の関与などの観点から、日本の国益上、関心度が高いであろう。また、イスラエル・パレスチナ紛争はアメリカの政治的関心が高いことなどから、日本においても関心度が高い側面もある。日本の国際報道がアメリカ政府や報道の関心に影響を受けていることはGNVの分析で検証されている。
その他の要因としては、メディアは「戦争」と「内戦」を区別して武力紛争に関する価値判断をしている可能性も考えられる。つまり、ガザとウクライナは国境を越えた武力紛争だという意味で「戦争」としている一方で、スーダンには「内戦」というラベルを貼っている。しかし、世界各地での武力紛争の実態をみると、どの紛争も1つの国の中だけに収まっているとは言えない。このような紛争の分け方自体に果たしてどれほどの意義があるのだろうか(※3)。
例えば、「内戦」と呼ばれているスーダン紛争だが、チャドや南スーダンなどから戦闘員が加わっているとされており、アラブ首長国連邦、エジプト、リビアなどが紛争当事者に武器提供など支援を行っていることも報告されている。加えて、スーダン紛争が長引くと「テロの温床」になる懸念もあるという報道もある。他の武力紛争においても多方面で越境がみられている。例えば、コンゴ民主共和国の紛争にはルワンダ軍の参戦が発覚している。また、隣接しているマリ、ニジェール、ブルキナファソの3国においては、個別の紛争に分けること自体が困難なくらいそれぞれの紛争が密接に絡み合っている。
「地獄の淵に立つ」人々
しかし、報道機関による価値判断において、物理的に当事者たちが越境しているかどうか、あるいは自国の国益や大国の政治的関心の観点だけが重要ではないはずだ。というのも、新聞の価値観や姿勢を示す社説において「人命」や「人権」を重要視している姿勢が示される場合が度々あるからだ。例えば、2024年1月1日の毎日新聞は社説において、「今こそ、『国家中心』から『人間中心』の視座に転換しなければならない。『すべての人の権利』保護をうたった75年前の世界人権宣言の精神に立ち返る時である」と主張している。

「危機のガザ支援 国連への拠出は命綱だ」と題された朝日新聞の社説(2024年2月9日)(写真:Nick Potts )
報道機関が、このような人道の精神に基づいた感情を込めた主張を行うことは少なくない。世界の全体像を捉えようとする、1年の初日の社説を見るだけでもそういった文言を確認することができる。例えば、読売新聞は社説(2024年1月1日)で「平和の大切さ、人命の尊さを世界に訴え、休戦、停戦、そして平和の回復と新しい秩序作りを呼び掛けることが、日本の使命であろう」と主張した。毎日新聞は社説(2024年1月1日)で、「国際社会に求められているのは一人でも多くの命を救うための迅速な行動である」とした。
しかし、実際のところ、報道において人命が平等なものとして重要視されているとは言い難い。上述した毎日新聞の社説で言及されている「命」とは、いわゆる「二つの戦争」によって脅かされるものにとどまっている。朝日新聞にも同じ傾向がみられる。2024年初日の社説(2024年1月1日)では「この地球の各所で人びとが爆発音や銃声に震え、おののく中、年が改まった。ウクライナとガザだけではない。ミャンマーやスーダンでも昨年は戦火が激しくなり、解決を見ないまま年をまたいだ」として、「二つの戦争」以外の一部の紛争を一度は視野に入れた。しかし、その言及はこの一言で終わった。同じ社説では「まさに地獄の淵に立つガザやウクライナの人びとに救いの手が届くよう願う」と、感情的に訴えた。視線が向けられているのはあくまでも「二つの戦争」による被害者である。
各報道機関は特にガザに対して、社説を通じて感情を込めたメッセージを度々発信している。例えば、読売新聞は社説(2024年11月25日)でガザでの死者数や懸念される飢饉を強調し、「ガザの住民約200万人が食料や水などを入手できず、生命の危険にさらされている」と述べた。また、朝日新聞の「飢餓迫るガザ 惨事防ぐ停戦を急げ」と題された社説(2024年3月28日)には「人道上の大惨事」や「人道悲劇」など、「人道」という単語が6回も登場する。
社説にみる新聞の人道的関心
では、世界各地で起きている人道危機に対して、報道機関の人道的関心にはどれほどの格差が生じているのだろうか。朝日新聞、毎日新聞、読売新聞の国際報道関連の社説において、どの国・地域に対して「人道」という言葉が使用されていたのか、1年分(2024年)の報道を調査した。
該当する社説は合わせて98件あった(※4)。その中、人道問題として言及されていた社説の件数の60.5%がガザに関するもので、いずれの新聞においても圧倒的に多かった。次に多かったのはウクライナ(10.5%)であった。レバノン、ミャンマー、シリアに関する言及はそれぞれ4〜5%程度を占めたが、それ以外の国への言及はほとんどなかった。
世界最大の人道危機と言われているスーダンについては、1.3%に過ぎなかった。その内訳としては、朝日新聞がスーダン紛争を中心に取り上げた1件の社説(2024年4月17日)と、日本の終戦の日に合わせた毎日新聞の社説(2024年8月16日)の中にあった「ロシアのウクライナ侵攻は長期化し、パレスチナ自治区ガザ地区の人道危機が極まる。スーダンなどでは内戦と飢餓が続く」という一言のみだった。読売新聞は2024年、社説でスーダンに言及することは一度もなかった。朝日新聞のスーダンに関する社説はスーダンの死者数、食糧不足、避難民などの人道問題にも注目し、この問題を大々的に取り上げたものとなった。しかし、このようにスーダンを中心に書かれた社説は2024年でこの1件のみだった。一方で、同紙においてガザの人道問題に注目した社説は21件あった。
「忘れられた」紛争:誰が忘れているのか?
スーダン紛争は日本の報道では「忘れられた」紛争と呼ばれることがある。そういった主張の中で、誰によってどのように「忘れられた」かははっきりしないが、世界情勢を伝える役割を担っている報道機関自身に目を向けることが必ずしもあるとはいえない。
朝日新聞はスーダン紛争を中心に書いた社説(2024年4月17日)において、「スーダンの内戦を『忘れられた紛争』にしてはならない」と主張した。同社説では、「国際社会の注目がウクライナや中東に集中し、他の地域への関心が弱まっているとすれば、ゆゆしき事態だ」とも述べた。しかし、朝日新聞自身がまさにその状態に陥っている。スーダン紛争について比較的長文の記事が掲載されるときもあったものの、2024年の総記事数でみれば、スーダン紛争に関する報道量はウクライナ報道の30分の1、ガザ報道の33分の1にとどまった。朝日新聞の別の記事(2024年6月11日)でも、「国際社会の関心が低いことから『忘れられた紛争』ともいわれる」と、一見、忘れた側を「国際社会」というあいまいな主体としている(※5)。しかしその後、日本でどのようにすれば関心を持ってもらえるのか、メディアとして「答えを探し続けている」とした。
また、毎日新聞はスーダン紛争に関する記事(2024年4月8日)において、忘れているのは「国際社会」だと示唆している。その見出しに、避難民が「ガザの5倍」と、スーダンの紛争の規模と深刻さを認識している姿勢を示した。しかし毎日新聞では報道の格差が朝日新聞よりも大きく広がっており、スーダン報道はウクライナ報道の71分の1、ガザ報道の88分の1に過ぎなかった。

スーダンの紛争を逃れた難民、チャド(写真:Henry Wilkins, VOA / Wikimedia Commons[Public domain])
スーダン紛争が現在、注目されていないのは明らかだが、紛争が勃発した当初(2023年4月)は、日本のメディアにある程度注目される時期があった。しかし、その注目は主に紛争が勃発した首都ハルツームにいた日本人とその退避に関する事象に当てられた。日本人の退避が終わると、激化していくスーダン紛争に関する報道量は急減していった。このように、日本の報道機関は一度、この紛争のことを記憶したものの、その後、「忘れた」と言えよう。
ステルス紛争、ステルス人道危機
今回の記事ではスーダンに関する報道に特に着目した。それは同国で起きている紛争が世界で 「記録上最大の人道危機」を引き起こしているためである。しかし上述した通り、スーダン以外にも大規模な人道危機をもたらしている武力紛争は数多く発生している。その中で、IRCの10大危機の3位となっている南スーダンの紛争もいわゆる「忘れられた」紛争と言える。日本の自衛隊が南スーダンに派遣された2012〜2017年の間、南スーダンはある程度日本のメディアによって注目されたが、撤収終了とともに、その報道量は減少していった。2024年も危機的な状態が続いているが、日本で報道された数少ない記事は、現在の南スーダン情勢ではなくて過去に南スーダンに派遣された日本の自衛隊員に関する問題が中心となっている。
しかし、「忘れられた」紛争とも呼ぶことすらできない紛争もある。それは一度記憶に残るほど日本のメディアによって大きく報道されたことがない紛争のことである。記憶したことがないものを「忘れる」こともできない。筆者は、もとから注目されることがない紛争のことを「ステルス紛争」と呼んでいる。これらの紛争はレーダーに登場しにくいステルス爆撃機のように、報道機関の関心度合いを表す「レーダー」に登場せずに隠れている。言い換えれば、報道機関がこれらの紛争の存在や規模を知りながらも報道しないことにしている。報道機関によって隠されているとも言えよう。
コンゴ民主共和国での紛争は最たる例であろう。この紛争は、朝鮮戦争以来において世界最多の死者数を出している武力紛争である。2024年にはコンゴ民主共和国とルワンダとの間で和平交渉が進められたものの決裂し、現在も記録的な避難民数と深刻な食糧不足が発生している。しかし、その報道量は慢性的に少ない。2024年の1年間で、コンゴ民主共和国での紛争が朝日新聞、毎日新聞、読売新聞で記事の対象になることは一度もなかった。

山積みされたウクライナへの人道支援(写真:EU Civil Protection and Humanitarian Aid / Flickr[CC BY-NC-ND 2.0])
人道危機の助長につながる報道不足
メディアの報道不足は、現実の世界に影響を及ぼす。国際報道において、報道機関は政府に寄り添う傾向にあるが、報道における注目は政府や世論による注目につながることも十分に考えられる。報道量が増えれば、政府による支援も増えると結論付ける研究もある。実際、2024年の日本から他国への人道支援の分配は報道量と類似の傾向をみせている。例えば、日本政府が2024年に国連を通じて提供した緊急支援を国別でみると、最多の支援の受け手はウクライナ(全体の10.4%)とパレスチナ(6.2%)だった。スーダン、南スーダン、コンゴ民主共和国は10位以内に入っていなかった。
NGOの活動においてもその傾向は報道と類似している。例えば、国際人道支援を行っているピースウィンズ・ジャパンは、主にウクライナとガザに注目しており、この紛争を「紛争・難民支援」の2本柱にしているようだ。2025年1月の時点で、ホームページにある「紛争・難民支援」を紹介する内容及び活動した国にはスーダンに関する言及を確認できない(※6)。一方で、2025年のアメリカ、ロサンゼルスで発生した山火事に対して、緊急支援の募金を集め、直ちに人員を派遣し支援活動を開始した。
アフリカの人道危機に関する日本での報道が増えれば、日本政府やNGOの行動に変化がみられるのだろうか。
まとめ
普段から紛争について報道がなされないという問題がひとつの原因で、世界各地で予防できるはずの多くの命が毎日落とされていく。ガザで繰り広げられている紛争が壮大な人道的悲劇であるというのは事実であり、大々的に報じることは必要不可欠である。しかし、同じ理由から、スーダン、南スーダン、サヘル3国、コンゴ民主共和国なども大々的に取り上げることが重要であろう。これらの紛争の間には、自国での国益や政治的関心の観点から大きな差があるかもしれない。しかし、報道の決定要因に人道的な観点も取り入れるのであれば、ある程度のバランスをとる必要がある。
報道機関が他国での人道危機に対して、感情を込めて、人命の重要性を訴える以上、「人命」への配慮を特定された場所の人間だけに限定するという傾向を考え直すことが急務なのではないだろうか。
※1 読売新聞データベース「ヨミダス」において、全国版に絞り下記のキーワードを検索し、それぞれのトピックが主題となっている記事をカウントした。
※2 朝日新聞・毎日新聞2社のオンラインデータベース(朝日新聞:朝日新聞クロスサーチ、毎日新聞:マイ索)を使用した。IRCが2024年に発表した10大人道危機及びウクライナが全国版の見出しにそれぞれの国名をキーワードに検索(パレスチナに関するキーワードは「パレスチナ OR ガザ OR ハマス」)し、紛争関連の内容が主題となっている記事をカウントした。複数の国にまたがる場合には、1を当該記事が属する国の数で割った数字でカウントしている。
※3 GNVでは「内戦」は誤解を招く言葉として捉えており、原則として使用しない。
※4 朝日新聞クロスサーチ、マイ索、ヨミダスにおいて、「人道 AND 社説」のキーワードを見出し及び本文を検索した。該当した記事を新聞別でみると、朝日新聞33件、毎日新聞35件、読売新聞30件あった。該当した記事の中、「人道」という言葉がどの国を指しているのかを特定しカウントした。複数の国にまたがる場合には、1を当該記事が属する国の数で割った数字でカウントしている。
※5 GNVは「国際社会」という言葉について、「使われる場面や文脈があまりにも広すぎるため、その意味を特定し捉えることはほぼ不可能だ」と誤解を招く言葉として捉えており、原則として使用しない。
※6 ただし、2024年3月には南スーダンの拠点からスーダン難民を対象とした支援活動を行ったことは確認できる。
ライター:Virgil Hawkins
グラフィック:Virgil Hawkins

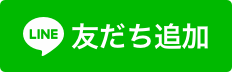









人道や人命の尊さを説く各社の社説に希望を持つ一方で、実際の報道との乖離にがっかりしました。社説を書いている人たちと紛争報道をする人たち、同じ新聞社にいながらこのようなギャップが生まれる背景は何にあるのでしょうか?
「世界10大人道危機」の中でも特にアフリカ大陸の国々の紛争が報道されていないことも気になりました。各社、サブサハラアフリカにはヨハネスブルグに支社をおいていたと思います。現地まで直接取材に入ることは難しくとも、距離的に近くにいることで得られる情報等はあるかと思います。どうにかして情報を届けてほしいと思うばかりです。
or61x0
「忘れられた」紛争という言葉が印象に残りました。あたかも世間が忘れたかのように表現していますが、忘れさせたのは誰なのか、そこの責任を無視しているのが非常に残念に感じました。メディアとして果たすべき責任を一市民としても、一読者としても考える必要があると強く感じました。