2023年初頭から、低中所得国をまとめて表す「グローバルサウス」という言葉が突如として日本の報道に出現するようになった(その経緯についてはこちらを参照)。2024年に入っても、日本の大手新聞は「グローバルサウス」という国のくくりに一定程度の関心を示し続けており、グローバルサウスとの関係の重要性に関する主張もみられる。例えば、毎日新聞は社説(2024年5月24日付)で、日本にとって「グローバルサウスとの関係強化は、国際社会での発言力を高める上で欠かせない。資源、食料、エネルギーの安定調達にもつながる」だと主張した。また、朝日新聞はグローバルサウスの国々の「存在感は高まっている」として、グローバルサウスをテーマにした国際シンポジウムを共同で主催した。
実際のところ、メディアがグローバルサウスにどれほど目を向けようとしているのかは、報道の内容を見てみると疑問だ。例えば、2024年8月17日にインドが第3回「グローバルサウスの声サミット」を主催し、21カ国の国家元首や34カ国の外務大臣を含む123カ国が参加した。インドの外交政策の一環だとはいえ、これほどの国の数が定期的にこの会議に参加しており、グローバルサウス諸国が抱える問題を共有する場としてある程度の注目に値するだろう。しかし、本会議は日本のメディアではほとんど取り上げられていない。朝日新聞は紙面に1つの短い記事を掲載したが、毎日新聞と読売新聞はこの会議が開催されたことには言及もしなかった。
「グローバルサウス」が日本の報道機関によってどのように報じられているのかをもう一度探る。

第3回「グローバルサウスの声サミット」で発言するインドの外務大臣(写真:MEAphotogallery / Flickr[CC BY-NC-ND 2.0])
減っていく「グローバルサウス」への言及回数
グローバルサウスは1969年以降、世界で幅広く利用されるようになった言葉である。貧困問題などを抱える低所得国という純粋な国くくりのみならず、植民地主義の負の遺産物や、現在も続く不公平な貿易システムに関する問題を共有する状態を表す概念にもなっている。
ではこれまで、グローバルサウスに関して、日本ではどのように報道されてきたのか。以前のGNVの分析でみてきたように、日本の大手新聞では、2023年までの数十年間で「グローバルサウス」という言葉は数回ずつしか掲載されていない。しかし2022年10月から、日本政府がこの言葉を利用し始めたことに合わせるように、日本の報道機関もグローバルサウスという表現を使うようになった。当時の日本政府のグローバルサウスに言及することの思惑としては、グローバルサウス諸国そのものやこれらの国々が抱える問題への着目ではなく、2023年5月に日本の広島市で開催されたのG7首脳会議に向けて、2022年にウクライナに侵攻したロシアに向けられていたと捉えることができる。つまり、グローバルサウスに言及する背景にはこれらの国々によるウクライナ支援増加や、ロシアへの圧力増加に協力を得ることが大きな狙いとしてあったといえる。日本のメディアも日本政府の方針や思惑に寄り添う立場をとった。
当時の日本の大手新聞の報道量の推移が、政治的な思惑を反映している。日本政府の関心に合わせ、「グローバルサウス」というキーワードが含まれる記事数が2023年1月から急増、G7首脳会議が開催された5月にピークを迎えた。そのG7首脳会議から1年以上が経過した現在、グローバルサウスの誌面への登場頻度はどう動いたのか。今回の調査では、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞における報道量を分析した以前の調査に加え、その後の1年分(2023年8月〜2024年7月)の報道量を計った(※1)。
このグラフからわかるように、3紙において、「グローバルサウス」という言葉を含む記事数は2023年5月のピーク以降は右肩下がりとなっている。全体的に、グローバルサウスへの関心が薄れているように見えるが、2024年8月以降、2回ほど、報道量の増加があったことがわかる。1回目の増加は2023年9月だ。グローバルサウスの言及回数が増えた背景には、同じ9月に開催されたG20の首脳会議と国連総会があった。これらの会議では、主にG7と中国・ロシアの対立に対するグローバルサウスの地域大国の立ち位置や、ロシア・ウクライナ戦争に対する姿勢といった文脈で言及されていた。
2回目の跳ね上がりは2024年6月に起きている。グローバルサウスの言及回数が増えたのは、6月にイタリアで開催されたG7首脳会議と、ウクライナへの支援の一環で多くの国がスイスで集まったいわゆる「平和サミット」に対して、グローバルサウスの国々の姿勢が注目されたからである。2023年9月の言及回数の跳ね上がり同様、グローバルサウスにおける事象が注目されたよりも、グローバルノースの主要国との関係や、ロシア・ウクライナ戦争との関係の文脈で紹介されていた。
報道の内容
これまでの分析は「グローバルサウス」という言葉が含まれる記事を対象としていた。しかしその大半の記事はグローバルサウスやその諸国が記事の主要なテーマではなかった。むしろ、他の事象(ロシア・ウクライナ戦争など)に関する記事にグローバルサウスが少し言及される程度であった。では、グローバルサウスがより本格的に注目された記事は1年間でどれほど大手新聞に掲載されていたのか。まず、2023年8月〜2024年7月までに、記事の見出しに「グローバルサウス」が含まれた記事を調査した。1年間で、朝日新聞に11記事、毎日新聞に9記事、読売新聞に6記事と、けっして多くない記事数だった(※2)。
では、これらの記事の内容はどうだったのか。毎日新聞と読売新聞においては、グローバルサウスが注目されたきっかけの大半は日本政府の政策や声明であった。例えば、毎日新聞は首相のグローバルサウス政策を分析する長文記事や社説を掲載した。また、岸田文雄首相がグローバルサウスの国々から「共感を得やすい『人間の尊厳』を強調し、気候変動や貧困などの課題の克服に協力する姿勢も打ち出した。」などと、政府の声明や主張を報じた。読売新聞もグローバルサウスとの連携の必要性を訴える岸田首相や林芳正外務大臣の発言などに注目した記事を掲載した。このような記事はいずれの新聞においても、グローバルサウスに関する記事の3分の2を占めていた(毎日新聞は9記事中の6記事、読売新聞では6記事中4記事)。

低所得者層住宅地、ペルー、リマ(写真:Xavi / Flickr[CC BY-NC-ND 2.0])
この2紙に比べ、朝日新聞は日本政府の姿勢に着目する記事は少なかった。その代わり、中国政府によるグローバルサウス関連政策やロシア・ウクライナ戦争などの文脈での欧米との関係に着目した記事が目立った。
いずれの新聞においても、グローバルサウスの「存在感」が高まっているとしながらも、日本、中国、欧米、G20などとの立ち位置や連携が最大の関心事項となっており、グローバルサウスそのものや、グローバルサウスが抱える問題などがほとんど報じられていない。例えば、今回の調査では、「グローバルサウス」が見出しに含まれた記事にグローバルサウスにとって優先順位が極めて高い貧困問題を取り上げる記事は1つもなかった。これらの記事に「貧困」という言葉自体が3紙合わせて、3回しか掲載されておらず、課題だとしながらも、言葉だけの言及にとどまっている(※3)。また、2023年11月17日にインドが主催した第2回「グローバルサウスの声サミット」について、毎日新聞と読売新聞(※4)が短い記事で紹介したが、朝日新聞は報じなかった。
グローバルサウス諸国への注目は減っている?
上記のデータをみる限り、日本の大手新聞はグローバルサウスへの関心は基本的にG7諸国や中国、ロシア、ウクライナの文脈で高まっており、前年に比べて2024年にはその関心は減少している。しかし、これまでの分析はあくまでも「グローバルサウス」という言葉が登場した記事だけを対象にしてきた。「グローバルサウス」という言葉が含まれなくても、グローバルサウスというくくりに含まれている個別の国や地域への関心が高まっている可能性はこのデータだけでは否定できない。他のデータと合わせて確認する必要がある。
まず、国別の報道をみてみよう。グローバルサウスに分類される人口がもっとも多い10カ国を対象にした報道(朝日新聞、毎日新聞)は過去10年間(2014〜2023年)でどう変わったのか、調査した(※5)。この10カ国には南アジア、東南アジア、南米、アフリカなどグローバルサウスの各地域からの国が含まれている。10カ国のいずれかの国名が見出しに含まれた記事数を合算して以下のグラフで表示している。結果からわかるように、2010年代に比べると、2020年代には、グローバルサウス10カ国に言及する報道量が大きく減少した。2014年の報道量が特に突出して多かったのは、その年にブラジルでサッカーのワールドカップが開催され、スポーツ関連の報道が他の年の国際報道より圧倒的に多かったためである。普段からも、日本の大手新聞におけるスポーツ報道は国際報道を大きく上回っている。しかし2014年を除外しても、2015年や2016年に比べ、2020年代ではグローバルサウス10カ国の報道量が半減している年もあるほどの減少傾向だ。
この減少の背景には、グローバルサウスのみならず、国際報道の総量の減少も影響していると考えられる。近年、日本の新聞による国際報道の量が減少しており、今回の調査期間中も減少している。しかし国際報道の総量の減少よりも、グローバルサウスの人口上位10カ国に関する報道量の減少の方が大きった(※6)。つまり、相対的にみてもこれらの国への注目が減少しているといえる。
しかし、グローバルサウスは、その中でも人口が多い国々もあるものの、人口がそれほど多くない国を含めると120カ国以上ある。例えば、アフリカ大陸の国々のうち50カ国以上がグローバルサウスに分類される。そんなアフリカに関する報道量をみてみよう。以下のグラフは「アフリカ」というキーワードが含まれる記事数(朝日新聞、毎日新聞、読売新聞)の推移(2014〜2023年)を表している。このデータは個別のアフリカ諸国に関する記事ではなくて、あくまでも「アフリカ」が言及された記事数だが、減少傾向(2019年だけが例外的に増えているものの)がみられた(※7)。
グローバルサウスの人口上位10カ国に関する報道とアフリカ関連報道のいずれにおいても、2020年頃に減少しており、以降も報道量が大きく回復しているとは言えない。この減少に新型コロナウイルスのパンデミックが大きく関わっている。このパンデミックは2020年の国際報道を独占する時期が長く、その中でも高所得国での感染状況が特に注目の対象となった。同じ2020年にグローバルサウスの国々でパンデミック以外の多くの深刻な事象が発生してるが、それらに関する報道量は極めて少なかった。また、パンデミックによって引き起こされた貧困および格差が急増し、グローバルサウスの国々への影響が極めて大きかったが、これも日本ではほとんど報じられなかった。
2022年のロシアによるウクライナ侵攻への圧倒的なメディアの注目もまた、グローバルサウスの国々への注目の減少につながった。2022年前半、大手3紙を対象としたGNVの過去の調査で明らかになったように、ロシア・ウクライナ戦争関連の報道の急増は、ただでさえ少なかったアフリカと中南米に関する報道量は例年の半分以下に減少させた。アフリカと中南米のそれぞれの地域が国際報道全体の1%にも満たなくなった。この戦争への対応の文脈で「グローバルサウス」という言葉が日本のメディアの間で多少流行したものの、その言葉の言及回数が増えた程度で、実質的なグローバルサウスの国々へのメディアの関心が増えたとは言い難い。
グローバルサウスへの理解を深めるには?
日本のメディアが、グローバルサウスを重要視している姿勢をとる背景にはさまざまな思惑がある。ウクライナから「ロシアを撤収に追い込む」ためにグローバルサウスの「協調を取り付けることが不可欠だ」という主張もあれば、冒頭にも紹介したように、世界での日本の「発言力を高め」、資源などの「安定調達」に必要だという主張もある。
日本の国益を拡大するためにグローバルサウスの国々との連携を強めたいことは理解しやすいが、「自由や民主主義、法の支配といった既存の国際秩序を維持・強化するためには、国際社会で存在感を強めているグローバルサウスとの協力は欠かせない。」といった見解が示されることもある。自由や民主主義、法の支配が「既存の国際秩序」を反映しているという疑わしい主張や、グローバルサウスの国々の多くには自由や民主主義、法の支配が欠けていることをさておき、既存の「国際秩序」で不利な立場に置かれているのはまさにグローバルサウスの国々だということは無視できない。

アフリカ連合の首脳会議、赤道ギニア、2011(写真:Embassy of Equatorial Guinea / Flickr[CC BY-ND 2.0])
グローバルサウスの国々にとって、自国が抱える多くの問題に対してグローバルノースの国々に協力してもらっているという実感はどこまであるのだろうか。紛争対策や人道支援において、ウクライナなど、グローバルノースの問題が優先されていることは明らかである(※8)。気候変動問題においても、グローバルノースがこれまで積み上げてきた問題から発生した被害を被っているのは主にグローバルサウスの国々である。また、世界の金融や貿易システムにおいても、蔓延するアンフェアトレード問題などからわかるように、グローバルノースにとって圧倒的に有利な「国際秩序」となっている。
この現状への理解を深め、実質的な改善が成し遂げられない限り、グローバルサウスの国々へのアピールの一環で、声明で「人間の尊厳」を強調したり、「連携」を訴えたりしたとしても、理解し合える協力的な関係に向けた前進の見込みは低いだろう。
また、報道の観点からみても、グローバルサウスとその諸国が抱える深刻な課題や世界を動かす仕組みにおける問題を見つめようとせずに、自国政府の声明を問わずに復唱することも、糸口を見出すことにはつながらないだろう。
※1 3紙のデータベース(朝日新聞のクロスサーチ、毎日新聞のマイ索、読売新聞のヨミダス)の全国版でキーワード検索を行った。
※2 朝日新聞のデータベース(朝日新聞クロスサーチ)に登場したシンポジウムのお知らせを省いた。また、読売新聞のデータベース(ヨミダス)では「記事」として扱われているが新聞ではなど、他の記事に付随した数行の解説記事(例:「〈解〉グローバル・サウス」)を5件省いた。
※3 「(グローバルサウスの現在地:3)「非同盟」維持、ブラジルの最善策 オリバー・ストゥンケル氏」朝日新聞、2023年9月7日、「グローバルサウス、世界に一石 国際シンポ」朝日新聞、2024年3月21日、「社説:グローバルサウス外交 明確な理念と戦略が必要」毎日新聞、2024年5月24日。
※4 「途上国課題を集約」読売新聞、2023年11月18日(113字)。
※5 2024年の時点でもっとも多かった国(インド、インドネシア、パキスタン、ナイジェリア、ブラジル、バングラデシュ、エチオピア、メキシコ、エジプト、フィリピン)が対象国となった。中国はグローバルサウスに分類されることは多いが、普段から突出して報道量が多いため省いた。見出しに国名が含まれる記事をカウントした。読売新聞のデータ(ヨミダス)では「見出しのみ」の検索ができないため、朝日新聞と毎日新聞のみ(全国版)を対象にした。
※6 例えば、2015〜2017年の3年間で3紙に掲載された記事の総数に比べ、2021〜2023年の記事の総数は約28%減少しているが、グローバルサウスの上位10カ国に関する記事の総数は同じ期間で約47%減少している。
※7 2015〜2017年の3年間で3紙に「アフリカ」が含まれた記事数に比べ、2021〜2023年の記事数は約27%減少しているので、国際報道の総数の減少で説明できると考えられる(※6を参照)。
※8 例えば、日本政府が2023年、国連を通じて世界に提供した緊急・人道支援を国別でみると、最も支援の対象になったのはウクライナで、全支援額の12.3%も占めた。それは2位の対象国の倍以上の金額であった。
ライター:Virgil Hawkins
グラフィック:Virgil Hawkins

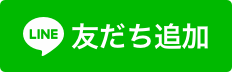









日本において国際報道、とりわけグローバルサウスについての関心が低いことがわかった。グローバルサウスという文脈においてもその国が面している問題に焦点を当てるよりかは、グローバルノースの利益のためにどうサウスを関わらせるかという意味合いの記事が多いんだと知った。試しに日経新聞でも調べてみたが、他の新聞と比べてグローバルサウスの話題で特異だったのは日系企業の海外事業についての話ぐらいで、グローバルサウスについての言及や記事は他新聞に比べて多いものの、国の中身についてしっかりと書いているものはなかった。
dhrvhm
この報道量の不平等は、グローバルノウスだけの問題ではなく、サウスの問題でもあると私は考えている。サウスもノウスも含めて世界が一丸となって考える必要がある問題がこの世にはたくさんあり、単なる供給者と受益者の関係になってはいけないと感じる。グローバルサウルの報道の問題は、世界の分断を感じさせる問題である。
分かりやすく新聞記事の分析がされていて、難しい話題のはずなのに頭に良く入ってきました。報道量の不平等について個人にできることもあるのでしょうか・・・。