2024年8月14日、ネパールの下院議会である法案が可決された。この法案は、ネパールで長年続き、2006年に終結した武力紛争に関わるものだ。「強制失踪者についての調査及び真実・和解委員会法に対する第三次修正法案」、または「移行期正義法案」として知られている。紛争が終結して18年も経過しているが、なぜ今もなおこのような動きが進んでいるのだろうか。

ネパールの首都、カトマンズの様子(写真:Justin KinerFollow / Flickr [CC BY-NC-ND 2.0])
ネパールの武力紛争とその背景
ネパールは、北は中国のチベット自治区、そのほかはインドと国境を接している内陸国だ。国土の75%が山岳地帯であり、特に北部はヒマラヤ山脈にあたるため、歴史的に中国よりもインドの影響が大きい。人口はおよそ3,000万人であり、その約81%がヒンドゥー教徒である。
現在に続くネパールの原型は、18世紀にゴルカ朝がネパールを統一し、カトマンズに首都を置いたときに形成された。しかし、その後ゴルカ朝のシャハ王家は他の有力貴族との政争の中で政治の主導権を握ることができず、実権をもたない形だけの王して君臨しているに過ぎなかった。19世紀に入るとインドを支配したイギリスの影響力が大きくなっていく。当時ネパールを実質的に支配していた有力貴族のラナ家は、イギリス領インド軍にネパール人の兵士の提供と外交自主権をイギリスに譲渡することで、ネパールの内政の自治を確保するという取り決めを行なった。
1947年になるとイギリスはインドから撤退したが、これによりラナ家はイギリスという後ろ盾を失った。1950年にインドのナショナリスト運動から刺激を受けた人々が、実権を取り戻そうとするシャハ王家と結びついてラナ家に対する革命運動を起こした。インドからの外交的援助もあって革命運動は成功し、シャハ王家は実権を取り戻した。また、政府機能はネパール会議派が率いる革命軍が引き継ぐことになった。そして1959年に憲法が成立し、議会選挙が行われた結果、ネパール会議派が第一党となった。しかし、1960年に王は議会を解散して政党を禁止した。1962年、王が大きな権限を持つ憲法が新しく成立した。

その後しばらく民主主義のシステムは弱く、王による直接政治が行われたが、民衆の反対に押される形で1980年に名目上政党は禁じたまま議会選挙を行った。この選挙では実質的にはネパール会議派を初めとする政党が非公式に活動していた。しかし、なおも民主主義を求める声はやむことはなく、1990年には大規模な抗議活動が発生した。この際に軍が鎮圧のために発砲して少なくとも50人が死亡した。そしてこの抗議活動を受けて、政府は政党を合法化した。また、議会制民主主義が組み込まれた憲法が成立し、翌年に議会選挙が実施された。この選挙の結果、ネパール会議派が第一党、穏健派の共産党(統一マルクス・レーニン主義派)が第二党となった。
一方、ネパールには穏健派とは別に強硬派の共産党(統一センター)が存在していた。これは1990年に設立された組織であり、共産主義の成立のために長期化する武力闘争も厭わないという姿勢をとっていたため、地下組織として活動していた。1990年に行われた選挙の際は、サミュクタ・ジャナ・モルチャという政党を組織して活動し、第三党となった。しかし、党内で武力による共産主義の実現を目指す急進派とあくまで合法的に共産化を目指す穏健派に分かれて対立し、1994年に分裂した。
このうちの急進派はマオイスト(毛主義者)と名乗って1996年に武力攻撃を開始し、この先10年間続くネパール紛争が始まった。当初は地方の警察施設などを対象とする攻撃が中心であり、政府も軍隊は動員せず警察で対処していた。なお、地方では貧困や社会的地位による差別に起因する社会的、経済的不平等を感じている人々が多く、マオイストはこのような人々から多くの支持を得ていたと指摘されている。
この紛争は、2002年にマオイストがネパール軍の軍事施設を攻撃してから激化した。また、地域の不安定化や共産化を恐れたアメリカやインドなどの国々はネパール政府に武器の提供を行った。政府軍は紛争の継続に必要な武器をこのような外国からの援助にほとんど依存していたため、結果として武器の提供は紛争を激化・長期化させることになった。また、諸外国は武器提供に際して十分な訓練や監視体制の整備を怠っていたことも紛争の被害規模の増大につながった(※1)。

ネパールのロルパ郡で、マイオストの集団の近くに放置されていたイギリス製のライフル(写真:Jonathan Alpeyrie / Wikimedia Commons [CC BY-SA 3.0])
一方、マオイストはどの国の政府からも直接の支援は受けていなかったと指摘されている。しかし、前述の通り地方の不平等を感じていた人々からの支持を得ていたマオイストは、地方での支配地域を拡大し続けた。そのような状況の中、2005年に当時の国王であったギャネンドラ・ビール・ビクラム・シャハ氏は問題の責任を議会に負わせて首相を罷免し、非常事態を宣言して直接統治を開始した。表現の自由をはじめとする憲法上の権利が停止され、兵士はジャーナリストや政治家などに圧力をかけるようになった。この動きにより政府は国民からの支持を失い、活動を停止された政治家はマオイストに接近することになった。
そして2005年の11月、マオイストとネパールの7つの政治政党との間で12ヶ条の合意が行われた。この合意は王の専制の停止と完全な民主主義の確立を共通の目的としたものであった。そして大規模な抗議活動の後、2006年の4月に王政は停止した。6月、新政府は現在の議会を解散してマオイストを含む暫定政権を設立することでマオイストと合意した。そして2006年11月、新政府とマオイストの間で包括的平和合意が結ばれ、10年に及ぶ武力紛争は終結した。
紛争がもたらした被害
この10年にわたる紛争による被害は大きい。紛争を通じての死者数は諸説あるが民間人を含めておよそ13,000人から19,000人だと主張されている。また、1996年から2005年の間にマオイストにより約4,500人が、政府軍により約8,200人が殺害されたとも指摘されている。また、未だ正確な死者数の情報は明らかになっていないが、ネパール首相府と内務省が共同で作成したデータによると、18,076人の民間人が紛争中に犠牲になったという。民間人の被害が大きい背景には、道路や通信のインフラが整っておらず、末端の兵士に対する監視体制が脆弱であったことや、政府軍もマオイストも非協力的な住民に対して攻撃を行うことが多かったことが主張されている。また民間人に対する攻撃は殺害以外の形をとることも多かった。国際連合人権高等弁務官事務所の報告書は、紛争を通じて違法殺害、強制失踪、拷問、恣意的逮捕、性暴力などの人権侵害が行われたとしている。

2002年に政府軍により家族を殺害された被害者による絵(写真:The Advocacy Project / Flickr [CC BY-NC-SA 2.0])
違法殺害は政府、マオイスト双方によって行われ、相手方の協力者だと疑われた一般市民が不確かな情報で殺害されることが多かったという。強制失踪(※2)は両者、特に政府によって行われたと指摘されている。また、紛争中に1,275件の失踪が記録された。2003年にはネパールは強制失踪が世界で最も多く起こった国だとも指摘されている。なお、強制失踪は、被害者だけでなくその家族にとっても大きな悪影響をもたらす。家族は被害の真相がわからないため、強制失踪か単なる行方不明か判断できず、気持ちの整理がつかなかったり、一家の収入源がなくなって経済的な困難に直面したりするからだ。そして被害者の多くは、二度と消息を聞くことはない。
拷問も双方によって行われ、少なくとも2,500件が報告されている。その目的は情報を引き出すためであったり、組織のルールの違反に対する制裁だったりとさまざまだが、これらの行為はさらに一般住民に対しても見せしめとして威圧的な効果を与えた。
恣意的逮捕は、定義上政府によってのみ行われる人権侵害の類型である(※3)。ネパールの法律では予防拘禁と呼ばれる制度がある。これは公共安全保障法、またはテロリストおよび破壊活動制御処罰法によるものであり、この制度を濫用することで司法の統制を弱め、より逮捕や拘束期間の延長をしやすくした。1999年には政治犯の拘禁は1,560人にも達したと記録されている。性暴力は両者によって行われたとされているが、報復や社会的な汚名を被ることを恐れて多くの被害者が被害を報告できずにいるため、全容はまだよくわかっていない。
人権侵害以外の影響としては、ネパールで重要な外貨獲得手段であった観光業が長期にわたる紛争で大きな打撃を受けた。また、被害を恐れて多くの人々が国外に流出し、伝統的な出稼ぎ先であったインドの他に、湾岸諸国や東南アジア諸国に出稼ぎに行くことになった。その結果、ネパール経済はその大部分が出稼ぎ労働者からの送金に依存することになった(※4)。
このように、ネパールは10年にわたる紛争によって多くの傷を負った。しかし、紛争からの立ち直りはスムーズとは言い難い。

2013年に行われたマオイストの全国統一会議を祝う式典の様子(写真:Krish Dulal / Wikimedia Commons [CC BY-SA 3.0])
移行期正義
ネパールの紛争後を見ていく前に、まずは一般的に紛争から立ち直るために何が必要かを考えてみよう。まず、紛争などで大規模な人権侵害が行われた後、そこから回復するための取り組みが行われる。このプロセスを、移行期正義という。この考え方は、1980年代後半から1990年代初めにかけてのラテンアメリカや東欧、南アフリカで発展した。当時これらの国々では権威主義から民主主義へ移り変わろうとしていく時期であり、新しい政府にとっては市民からの支持が必要となる中で、前の権威主義的な政府が行った大規模な人権侵害に対してどう向き合うかが重要であった。
そのような社会状況で生まれた移行期正義という概念は、被害者を中心とした考えに基づき、真実を明らかにして補償と責任追求を実践し、同じような人権侵害が二度と起こらないようにすることを目的としている。長期的には、民主主義の強化や当事者間の和解を促すことも移行期正義に含めることができる。これらは人権侵害の加害者、被害者、遺族が入り混じる国民が、ひとつの国の中で共存していくためには必要なプロセスである。
また、移行期正義の理論は、紛争が起こるたびに新しいアプローチを取り入れて発展を続けている。紛争ごとにその背景、状況、そして人権侵害の態様にも違いが出るため、取るべきアプローチもそれらに合わせて柔軟に変えていく必要があるからだ。具体的には、戦闘員の社会復帰、少数コミュニティ間の和解、司法手続きの活用などが挙げられる。またシエラレオネやウガンダでは、和解を進めるために法的手続きだけではなく伝統的な儀式を取り入れるなど、より視野の広いアプローチを採用した例もある。

2017年に開かれた国連開発計画が開催した、法の支配年次会合の、移行期正義と和解についてのワークショップの様子(写真:United Nations Development Programme / Flickr [CC BY-NC-ND 2.0])
また、移行期正義は大規模な人権侵害の後に行われるものであるため、被害は大きく、背景には社会構造や格差、宗教が絡んでいることが多い。そして紛争直後の政府は多くの場合脆弱であることも考えられる。そのような状況では、一つのアプローチを行うだけでは問題の解決につながりにくい。そこで、今日の移行期正義は全体的アプローチが必要だと主張されている。
全体的アプローチは、複数のアプローチを同時に行うことで移行期正義の実現を目指す。具体的には、法的、政治的システムの改革、真実追求のメカニズムの構築と実践(※5)、人権侵害を行った者の処罰、被害者への補償、権利の返還、記憶の継承などが挙げられる。これらのアプローチはどれか一つでは不十分に終わると考えらえる。例えば、責任者の処罰だけが行われたとしても単なる政治的なパフォーマンスと受け取られてしまう恐れがある。また、被害者への補償だけではその金銭は口止め料とみなされてしまうかもしれない。いずれの場合であっても被害者中心であり、被害を繰り返さないための取り組みとしての移行期正義は達成されない。
移行期正義の実践は長い年月が必要であり、決まった正解は存在しない。移行期正義は、行われた侵害の規模、性質に加えて、侵害が起こった社会の文化、歴史、法律や政治システム、宗教、経済、コミュニティの分布などを考慮して、被害者中心の理念のもと進められなければならない。このように様々な要素が絡み合う移行期正義というプロセスについて、ネパールはどのように向き合ってきたのだろうか?
紛争後のネパール
ここからは、まず紛争後のネパールの動きについて見ていこう。
前述の通り、ネパール紛争は2006年に包括的平和合意が結ばれたことで終結した。この合意では、人権を侵害した者に対する調査を行うこと、免責を助長しないこと、そして被害者への救済が明記された。そして、2007年1月に暫定憲法が採用された。しかし、この暫定憲法に対してネパール南部に住むマデシ系の人々が反対した。マデシ系の人々はネパールの人口の3分の1を占めているが、経済的、政治的に疎外化されていると考えていた。21日間続いたこの反対運動の中、地方自治と連邦制の採用を求めて抗議していた人々は治安当局と衝突し、約40人が犠牲になった。
当時の首相、ギリジャー・プラサード・コイララ氏は暫定憲法の改正を約束し、この暴動は収束した。そして2007年4月、暫定憲法の中に「連邦制」という言葉が付け足された。また、暫定憲法33条には救済金の支給や人権侵害についての調査をはじめとする移行期正義についての文言も盛り込まれている。
この暫定憲法のもと、2008年に憲法議会選挙が行われた。第一党は政党化したマオイストとなり、ネパール会議派と共産党(統一マルクス・レーニン主義派)が続いた。ただし、マオイストも単独の過半数には届かなかった。この選挙を経て王政は正式に廃止された。また、憲法議会が始まり、正式な憲法を作る準備が整った。

2013年に行われた議会選挙のときの投票所の様子(写真:Krish Dulal / Wikimedia Commons [CC BY-SA 3.0])
しかし、真実・和解委員会と強制失踪者調査委員会の設立を巡って意見が一致せず、2012年に議会は解散した。2013年に最高裁判所長官のキル・ラージ・レグミ氏が事実上の首相となり、このときに真実・和解委員会設置命令が公布された。しかしこれは政治的妥協の産物であり、人権侵害を行った責任者への恩赦や、委員会の権限が小さいことなどの点で移行期正義の理念にそぐわないものであった。そのため被害者団体の連合は訴訟を提起した。その結果、2014年に最高裁はこの命令を国際人権法、最高裁判例、暫定憲法にそれぞれ違反していると判断した。このあと、新しい強制失踪者調査及び真実・和解法(TRC法)が成立した。これにより2015年に真実・和解委員会と強制失踪者調査委員会が設置されたが、最高裁はこの法律の恩赦規定が違法であると判断した。
2018年、TRC法の改正法案の草案が被害者団体に渡された。しかしこの改正法案も被害者との協議なしに進められた、透明性に欠いたものであった。さらに、この改正法案についての政府との協議期間は2週間に満たず、大きな変更も行われなかった。結局この改正法案は政府に対するさらなる不信感につながった。
2023年、新しいTRC法の改正法案が議会に提出された。これは、補償や救済金を得られる対象の拡大など、いくつかの点で改善は見られるものの、作成段階における被害者との協議はまだ不十分であり、従来からの懸念事項である恩赦や委員会の権限の弱さなどについては大きな変化がないものだった。そして、2024年にこの法案は議会の3党で意見が一致し、議会を通過した。この動きについての意見は分かれている。反対派は改善が十分ではないと主張しているが、許容派は停滞していた補償などのプロセスが前進することを期待していると主張している。
また、政治的プロセスが停滞していた理由として、ネパールの政権の不安定さが挙げられるかもしれない。ネパールでは2008年から2020年までの12年間で、11人の首相が生まれるほど政権は不安定だった。ネパールではマオイスト、共産党(統一マルクス・レーニン主義)、ネパール会議派の3つの大きな党があるが、選挙でどの政党が第一党になっても議席の過半数を取ることができず、政権を運営するために他の党と協力しなければならない状況が続いている。また、成立した連立政権もすぐに崩壊してしまうことが多く、長期の安定した政権が生まれにくいとされている。そのような状況下では、政治を前に進めることは難しい。
さらに、ネパールは中国やインドとの関係も慎重に調整する必要があったとも指摘されている。この3カ国の関係を考えるにはチベットを軸にするとわかりやすい。ネパールはチベットからインドに至るためのルート上にあったため、中国にとってはチベットを併合する上で都合が悪いものだった。そのため、2008年にマオイストが第一党となったときに関係を深め、チベットからの難民を受け入れないように要求した。一方、インドはネパールと歴史的に関わりが深い国である上に、チベットを支持しているため、ネパールと中国の接近に懸念を抱いている。対立する大国に挟まれているネパールは、バランスを取るために外交関係にも気を払う必要がある。
ネパールの移行期「正義」
ここからはネパールの動きについて、先に見た移行期正義の考え方に基づいて詳しく見ていこう。移行期正義は多様な要素を含んでいることは先に見てきたとおりだが、ここでは責任追及、真実の追求、被害者への補償、記憶の継承の4点に絞って考えてみよう。

委員会に参加して発言する強制失踪者の家族(写真:The Advocacy Project / Flickr [CC BY-NC-SA 2.0])
責任追及とは、人権侵害を行ったものに対する責任を明らかにして適切な処罰を行うことだが、この点についてネパールの対応には大きく2つの点で問題があると指摘されている。1つ目は恩赦だ。2024年に成立したTRC法改正法では、紛争中に行われた人権侵害は、「人権侵害」か「深刻な人権侵害」に分類される。そして「人権侵害」であれば恩赦が与えられる可能性がある。恩赦は真実・和解委員会が、被害者の同意に加えて一定の条件(※6)を満たしていると判断したときに出されるものであり、恩赦が出されなければ特別法廷に付託される。「深刻な人権侵害」の場合はそのまま特別法廷に付託され、訴追される可能性がある。
しかし、「深刻な人権侵害」は強制性交や深刻な性暴力、意図的または恣意的な殺害、強制失踪、非人道的または深刻な拷問に限られており、これらは国際法に合致しない。例えば、ネパールも1991年に批准している拷問等禁止条約において拷問は、その他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱いと同列の扱いとなっている。つまり、拷問とは本来非人道的なものであり、あえて「非人道的または深刻な」という言葉で限定するのは適切ではないと指摘されている(※7)。
2つ目は、司法長官の権限だ。この改正法によると、司法長官は性暴力の場合を除いて、「深刻な人権侵害」を行った者に対して拘禁期間の75%の減刑を行うことができる。これにより恩赦ほどではないが人権侵害を行ったものに有利な処置がなされるおそれがある。

強制失踪の被害にあった人物を追悼する人々(写真:The Advocacy Project / Flickr [CC BY-NC-SA 2.0])
次に、真実の追求について見ていこう。真実の追求は、主に真実・和解委員会と強制失踪者調査委員会によって進められる事になっている。これらの委員会は2015年に設置され、約64,000件の人権侵害が申告された。しかし、2019年になっても真実・和解委員会は10%未満の事案についての予備調査が完了しているに過ぎず、強制失踪者調査委員会は75%程度の予備調査が済んでいるだけだった。つまり、どちらの委員会も1件も事案処理を完了させていなかった。この委員会の実効性の欠如は大きな問題となっている。
被害者への補償については、2007年に賠償計画が始まった。2017年までにこの計画により数千万米ドル(※8)が分配されたという。しかし、これは被害者の声を黙らせるための手段として使われていると指摘されている(※9)。また、拷問や性暴力の被害者はこの計画では対象外であることが問題になっている。ただし、2024年に成立したTCR法改正法ではこの除外された被害者も補償の対象に含まれている。一方、補償のためには被害をまず明らかにしなければならないが、真実の追求のプロセスが停滞している場合適切な賠償を受けられないことが懸念されている。
記憶の継承については、政府が主導となって行われているネパール紛争の記念活動は、「殉教者の門」と呼ばれているモニュメントの設置のみであると指摘されている。これは正確には現在の主要政党であるマオイストの戦没者を追悼している。この意味で、政府はネパール紛争で起きた悲劇の記憶の継承を十分に行なっているとはいえない。人々が自発的に記念運動を行うこともあるが、資金の不足や政府の支援の欠如によりそれらの活動が困難な場合もあると指摘されている。一方で、ネパールの新しい憲法は連邦制を採用しており、地方政府がある程度の裁量を持っているため、地方政府が主導して記憶の継承活動を進めていくことが提案されている。

カトマンズにある「殉教者の門」(写真:Kuber Sodari / Wikimedia Commons [CC BY-SA 3.0])
本当の移行期正義へ
移行期正義を考えるとき、何よりもまず被害者が中心にいなければならない。意思決定の場に被害者が参加し、様々な取り組みが全体的に進められることで移行期の正義は前に進んでいく。ネパールで進められた移行期のプロセスは、この点で正義を体現しているとは言えない。被害者は意思決定の場から排除され、政治的妥協による恩赦や減刑を認める規定が法律に盛り込まれ、設置された委員会はほとんど機能してこなかった。また、被害者が紛争から前を向くことの必要性を考えると、停滞を繰り返すネパールの移行期のプロセスはあまりに遅いといえるだろう。
2024年に成立した法律もいまだ多くの欠点が指摘されており、完全なものだとは言えない。しかし、停滞していた移行期のプロセスの進展であるとも評価されている。とはいえ成立した法律が適切に実行されるかどうかはまだわからない。ネパールが被害者中心の移行期正義を進展させられるかどうか、今後も注視していくことが重要だ。
※1 武器援助はアメリカ、インドの他に、イギリスやベルギーも行っていた。また、マオイストはこれらの援助で政府に提供された武器を奪うこともあったという。
※2 典型的なケースでは、敵側に関係があると疑われた人物を拉致し、暴力を振るったり当局の施設で監禁したりしていた。また、被害者の家族が失踪の被害を届けにきても情報が提供されることはなかった。
※3 ただし、同様の行為はマオイストも行なっていたとされている。
※4 ただし、これらの出稼ぎ労働者の送金によりネパール経済は破綻を免れたとも考えられている。
※5 真実の追及とは、大規模な人権侵害の実態や原因、そして被害者の特定などを調査し、明らかにすることである。このアプローチは、被害の補償や人権侵害の再発の防止策を検討するときにも重要な手がかりを提供する。
※6 これらの条件には、真実の告白、被害者に対する謝罪、賠償金の支払いなどがある。
※7 加えて、この2つの類型は、性暴力の場合を除いて「非武装の人物または集団に対して、標的として狙ってまたは計画的に」なされたものである必要があり、この規定により多くの行為が移行期「正義」のプロセスの対象外になる可能性がある。
※8 2017年当時の数十億ネパール・ルピーに相当。
※9 被害者が、真実や調査、訴追のない賠償金の受け取りを断った場合、暫定救済金と名前を変えて支給されるという。
ライター:Seita Morimoto
グラフィック:Yumi Ariyoshi

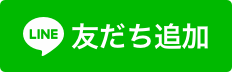









日本に出稼ぎや留学で来るネパール人が急増しているのは、母国での仕事がないからと聞いたことがあったが、歴史を学ぶことで彼らが外国に行かざるを得ない状況がわかった。
移行期正義という考え方があることも初めて知った。
ネパールは植民地支配を受けていないにも関わらず、民主主義がうまく機能せず、政治が不安定であることも紛争処理が進まない原因であること。また、多くの人権侵害のケースが「深刻な人権侵害」の定義から外れたり、紛争処理の委員会が受理した事案のうち、1つも調査が完了していないなど、法的紛争処理について国連機関や他国の支援が必要なのではと思った。ネパール人の友人にこの問題についてどう思っているのか聞いてみたい。
移行期正義という言葉について聞いたことはあったが、そ意味を初めて詳しく知ることができた。紛争は和解されたら注目が薄れることが多い。しかし、その後のプロセスが適正出なければまた争いを生むことになりかねない。今後はそんな紛争後のプロセスのついても注目していきたい。
政府軍によって家族を殺害された被害者による絵が見ていてとても痛々しいものだった。移行期正義という概念を初めて知った。移行期正義のアプローチに取り組む主体がその国の人々だけでは、紛争があったこともありスムーズな実施が難しくなるだろうから、国連やNGOなど紛争に関して中立である組織も大きく関わっているのだろうかと思った。