2023年も、メディアが注目した話題としなかった話題の差は大きかった。世界では、多くの人や国、さらには世界全体などに大きな影響を与えたにも関わらず、日本のメディアによってほとんど報道されなかった、あるいは全く報道されなかった出来事が多数起こっているのである。
武力紛争に関して、2023年に報道を独占した出来事は、2022年から続くロシア・ウクライナ紛争とイスラエル・パレスチナ紛争だった。その一方で、報道であまり取り上げられなかったアフリカ、アジアなどでは複数の紛争が繰り広げられていた。例えば、コンゴ民主共和国では、長らく続く紛争によって、過去最多の690万人にものぼる避難民が発生しているにも関わらず、2023年には日本の大手新聞で全く報道されていない。また、5人の富豪を乗せたタイタニック号見学の潜水艇が水没したことについては日本で注目されたにも関わらず、同週に地中海で沈没した船に乗っていた難民・移民のうち600人が亡くなったことについてはほとんど報道されていなかった。他にも、イギリスのチャールズ国王の象徴的な戴冠式は日本でも大きく取り上げられた裏で、多数の人々の生活を左右した政治的な出来事が世界各地で発生したにも関わらず注目されなかった。
そこで、GNVでは、2018年から2022年に引き続き、2023年に起こった、多くの人や国、または世界全体に影響を及ぼしたにも関わらず、それに見合った報道がなされていない出来事を独自に選出し、10位までのランキング形式にまとめた。
以下に、GNVが選出した10の出来事を順番に発表していく。順番を決める際に用いた詳細な基準(※1)や報道量の測り方(※2)は脚注に記載している。それでは、2023年の潜んだ10大ニュースを1位から見ていこう。
第1位 G20諸国で化石燃料に対する補助金が4倍に急増
2023年の持続可能な開発に関する国際研究所(IISD)の調査によると、2022年、G20諸国が化石燃料に対して1兆米ドルを超える補助金を投入したことが明らかになった。これは、2021年に比べておよそ4倍に当たる。補助金は主に消費者向けと生産者向けの2種類であるが、今回急増したのは消費者に対する補助金である。補助金の目的は、ロシアによるウクライナへの侵攻とその後の対ロシア経済制裁によって、化石燃料価格が高騰したことに対して、販売価格を維持するためであった。ただこの方針は、2009年の化石燃料補助金の段階的廃止を決めたG20での取り決めと逆行している、と非難されている。化石燃料補助金は、価格上昇の影響を受ける人々を支援するために必要だという見解もある一方で、化石燃料を使い続けるインセンティブを生み出してしまうとも言われているのである。さらに、2023年にアラブ首長国連邦(UAE)で開催された国連気候変動枠組条約第28 回締約国会議(COP28)では、化石燃料からの「移行」が合意されたが、化石燃料への補助金はこれを妨げる。他にもCOP28では、UAEの国営石油会社の最高経営責任者、スルタン・アル・ジャベル氏が議長を務め、国営の石油・ガス会社の取引を促進するためにこの会議を利用した疑いもある。また、COP28には化石燃料関連企業のロビイストが少なくとも2,456人参加したと見られており、過去最多の人数となった。
報道量
朝日新聞:0記事/0字
毎日新聞:1記事/1,183字
読売新聞:0記事/0字

カナダにある石油精製所(写真:Kurayba / Flickr [CC BY-SA 2.0])
第2位 サウジアラビア国境警備隊による移民の虐殺、数百人が犠牲に
サウジアラビア国境警備隊が、イエメンとサウジアラビアの国境を越えようとしたエチオピア人移民・難民の集団に向けて無差別に発砲し、殺害してきたことが人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチの調査によって判明した。死亡者数は、2022年3月から2023年6月の間で少なくとも665人、多ければ数千人と言われている。虐殺が行われたとされるこの場所は、通称「東のルート」と呼ばれる回廊上にあたる。エチオピアやソマリアが位置するアフリカの角から、海上を通ってイエメンに渡り、サウジアラビアに向かうルートであり、世界で最も混雑している海上移民回廊である。移民・難民が移動する理由はいくつかあり、貧困や干ばつ、武力紛争や政治的不安定などが挙げられる。サウジアラビアは労働力の多くを移民労働者に頼っている側面もあり、移民は雇用機会などを求めてサウジアラビアに向かうのだ。しかし、移動ルート上にあるイエメンでは、2015年以降サウジアラビアなどの軍事介入もあり、世界最悪とも呼ばれる程の紛争が続いてきた。そのため、イエメンに上陸、通過することも移民にとっては命がけである。また今回の虐殺について、サウジアラビアは否認しているが、エチオピアとサウジアラビアで共同調査を開始する予定である。
報道量
朝日新聞:0記事/0字
毎日新聞:1記事/621字
読売新聞:0記事/0字
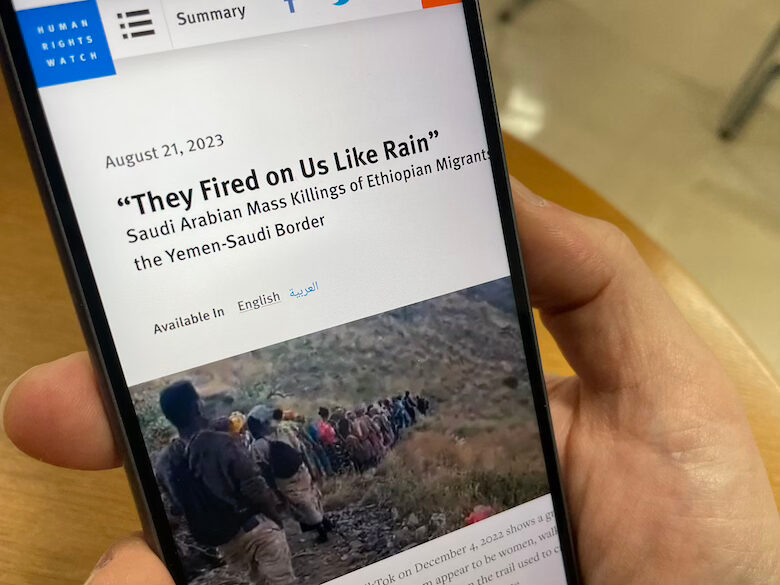
ヒューマン・ライツ・ウォッチのサウジアラビアによる虐殺についての記事 2023年12月20日撮影(写真: Yuna Nakahigashi)
第3位 世界の教師不足が4,400万人に
現在、世界には学校に通えていない子どもが8,400万人もいると推定されている。原因は、長引く紛争や貧困、インフラの不整備など様々だが、これらに付随する原因として教師不足が挙げられる。2023年10月の国連教育科学文化機関(UNESCO)の発表によると、世界で4,400万人の教師が不足しているという。この数字は、2016年に6,900万人だった状況からは改善されているが、依然大きく不足している。このような教師不足の原因は複雑であり、各地域によっても大きく異なる。例えば、教師不足が最も顕著なサハラ以南アフリカでは、教育に対して十分な予算がつけられていないことが最大の原因とされている。一方、ヨーロッパと北アメリカでは、労働条件や給与への不満による離職率の高さが主な原因のひとつである。このような状況で、すでに持続可能な開発目標(SDGs)のゴール4「質の高い教育をみんなに」の目標到達は不可能と見られている。というのも、1番目のターゲット(※3)を達成、すなわち2030年までに全ての子どもが中等教育を修了できるようにするためには2021年までに小学校に入学する必要があるのだ。
報道量
朝日新聞:0記事/0字
毎日新聞:0記事/0字
読売新聞:0記事/0字

木の下で授業をする先生と児童たち(ナイジェリア)(写真:USAID in Africa / Flickr [United States government work])
第4位 イラク、100年間で最悪の水不足
イラクでは、ここ100年間で最悪の水不足が起こっている。この水不足は、農民の約60%に影響を与えていると言われている。具体的には耕地が大きく減少し、家畜や魚が死亡するなどの被害を受けている。このような深刻な水不足に陥った原因は様々であり、気候変動などによる干ばつや石油採掘の際に多くの水を使用する石油産業の過剰化、長期間にわたる紛争などが挙げられる。紛争については、1990年代の湾岸戦争とその後のサダム・フセイン政権に対する経済制裁や2003年のアメリカによる侵攻、2014年のイスラム国の台頭などがある。また、紛争によるインフラの破壊や政情不安、他にも根強く残る汚職などが、水管理政策の不備にも影響を与えている。他にも、クルディスタン地域(※4)では人口の急増も原因の一つとされている。また、上流諸国との関係も水不足に大きな影響を与えている。イラクにも流れるティグリス川とユーフラテス川の上流及び支流に位置するトルコとイランでは、新たなダムの建設が行われている。実際に、1975年に比べ、トルコからイラクへの水の流入は約80%も減少している。
報道量
朝日新聞:0記事/0字
毎日新聞:0記事/0字
読売新聞:0記事/0字

農民の大切な資産である水牛(イラク)(写真:Peter Chou Kee Liu / Flickr [CC BY-NC-ND 2.0])
第5位 結核薬のジェネリック製薬が可能に
2023年9月、世界の中低所得国134カ国で多剤耐性結核に対して使われる結核薬ベダキリンのジェネリック製薬が可能になった。世界最大の製薬会社、ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J)が結核薬ベダキリンの特許を放棄したのだ。結核とは、細菌によって引き起こされ、空気を介して感染が広がる三大感染症のひとつであり、これが原因で2022年もなお世界中で130万人もの人が亡くなっている。この結核は抗生物質で治療可能である。そのため、治療薬のジェネリック化は、多剤耐性結核患者の4人に3人に相当する、45万人に影響を与えると予測されている。結核薬のジェネリック化は、2023年3月にインドの知的財産控訴委員会 がJ&Jによるベダキリンの特許延長申請を却下したことが契機である。その後国境なき医師団などからJ&Jに特許延長申請取り下げ要請などが行われたことで、J&Jが中低所得国での延長特許を放棄することを発表した。近年まで6ヶ月あたりの薬剤価格が400米ドルだったベダキリンは、2023年8月に130米ドルに下がった。特許放棄によりさらに80米ドル〜102米ドルに下がる見込みとされている。一方で、日本の製薬会社、大塚製薬は別の結核治療薬の特許を未だ所持しており、それを放棄することが求められている。
報道量
朝日新聞:0記事/0字
毎日新聞:0記事/0字
読売新聞:0記事/0字

北アメリカにあるジョンソン・エンド・ジョンソンのオフィス(写真:Open Grid Scheduler / Grid Engine / Flickr [CC0 1.0])
第6位 アフリカ初の気候サミット開催
2023年9月、史上初のアフリカ気候サミットが開催された。その背景には、年々拡大する気候変動による影響がある。アフリカの炭素排出量は、現在までの世界の積算炭素排出量のうち、たった3.8%のみであるが、気候変動による被害を大きく受けてきた。例えば、東アフリカでの干ばつの悪化や南東アフリカを襲ったサイクロン、リビアでの大規模な洪水などがあり、2023年はアフリカ全土での災害死者数が最も多い年のひとつになっている。気候サミットは大きく2つの目的を掲げていた。1つ目は、損失と損害(※5)の保証と今後の気候変動対策のための新たな資金調達メカニズムを構築すること。2つ目は再生可能エネルギーのインフラ整備の道筋を明確にすることである。サミットの成果としては、世界へアフリカ共通の立場を示す「ナイロビ宣言」が採択された。その中で、二酸化炭素排出量の多い国が低所得国への責任を負うための炭素税導入と、世界でのグリーン投資の多国間金融システム改革、すなわち低所得国への無償融資の増加が提案された。このナイロビ宣言を通して、COP28でのいくつかの宣言においてアフリカの要望が反映されている。
報道量
朝日新聞:0記事/0字
毎日新聞:1記事/709字
読売新聞:1記事/479字

ケニアのナイロビで行われた、初のアフリカ気候サミット(写真:Climate Centre / Flickr [CC BY-NC 2.0])
第7位 EU、非OECD諸国へのプラスチック廃棄物輸出禁止に合意
2023年11月17日、欧州連合(EU)議会は廃棄物輸出規則を更新し、経済協力開発機構(OECD)諸国以外への非有害プラスチック廃棄物の輸出禁止についての暫定協定に同意した。現在ヨーロッパでは、毎年約2,600万トンのプラスチック廃棄物が排出されているが、そのうちリサイクルされているのは30%未満である。そして、輸出された廃棄物の半分はEU諸国以外の国へと向かっている。2022年には、主にトルコ、マレーシア、インドネシアといった、処理や処分が低価格で可能な非EU諸国へ輸出されたプラスチック廃棄物は110万トンを超えた。ただし、EU域内廃棄物の輸出先の半分を占めるトルコは輸出が制限されていないという問題もある。トルコはEUには加盟していないが、OECD諸国には含まれているため、今回の規制の対象外となる。しかし、トルコではプラスチック廃棄物が必ずしも環境に配慮した方法で処理されているとはいえない状況である。そのため、環境破壊や廃棄物処理場の周辺住民への悪影響が続く可能性が懸念されている。
報道量
朝日新聞:0記事/0字
毎日新聞:0記事/0字
読売新聞:0記事/0字

1度の使用後プラスチック廃棄物になりやすいペットボトルの水(写真:Steven Depolo / Flickr [CC BY 2.0])
第8位 ブルキナファソで紛争・テロが激化
ブルキナファソでは、2015年から続く武力紛争が激化している。この紛争は、隣国マリから武装勢力が侵入してきたことで始まり、以降1万7,000人以上が死亡しているが、2022年以降死者が急増している。具体的には、2023年の紛争死者数は8,600人にのぼると推定されている。また、2022年には、世界テロ指数がアフガニスタンに次ぎ第2位となっており、状況の深刻さがうかがえる。このような状況で、避難民の数は増加し、国民の10人に1人である210万人が自宅を追われており、国民の4分の1もの人々が人道支援を必要としている。また、教育においても、国内の4分の1の学校が閉鎖し、100万人の生徒に影響を与えている。このブルキナファソの紛争は一国で留まるものでなく、マリやニジェールなどとも密接に関係している。また、国家間関係の移行も見られる。2022年に2度発生したクーデター後の政権のもと、駐在していたフランス軍が撤退し、ブルキナファソはフランスが主導していたG5サヘル同盟(※6)からも離脱した。一方で、ブルキナファソ、マリ、ニジェールの3国で相互防衛協定「サヘル諸国同盟」が設立された。
報道量
朝日新聞:0記事/0字
毎日新聞:1記事/279字
読売新聞:1記事/415字

パトロール演習を行うブルキナファソ兵(写真:US Africa Command / Flickr [CC BY 2.0])
第9位 国連世界食糧計画(WFP)の食料支援が減少
2023年9月、WFPは資金不足により世界での食料支援が急減しており、緊急の食料不足に陥る人が今後12ヶ月で50%増加する可能性があることを発表した。世界では現在、4,000万人が緊急レベルの飢餓に陥っているが、2024年9月までに更に2,400万人が直面する可能性があると推計している。これほど深刻化している原因は、紛争や気候変動による食料不足に加え、新型コロナウイルス感染症の長期的流行やロシア・ウクライナ紛争による食料価格の高騰が重なったことなどが挙げられる。さらに、インフレやサプライチェーンの乱れは、WFPの食料支援コストも増加させている。しかし、各国の支援予算の多くはウクライナに対する支援に流出しているため、WFPの資金は集まりにくくなっており、そのしわ寄せは多くの国で見られる。コンゴ民主共和国では、約2,600万人が深刻な食料不安に直面している。しかし、7億7,400万米ドルの資金不足により、支援縮小を余儀なくされている。またアフガニスタンでは、約1,530万人以上が深刻な食料不足に陥っている。しかし、資金不足により食料支援を提供する人数を1,000万人に削減する見込みだ。他にも、シリアやマリ、イエメンなどで同様の傾向が見られる。
報道量
朝日新聞:2記事/1,144字
毎日新聞:1記事/2,079字
読売新聞:0記事/0字

食料支援を行う国連WFP(ネパール)(写真:WFP.Aviation / Wikimedia Commons [CC BY-SA 4.0])
第10位 アフガニスタンでのケシ栽培が95%減少
2023年、アフガニスタンでは、ヘロインやアヘンといったオピオイド系麻薬の原料となる植物であるケシの栽培が95%減少した。この理由は、2021年に政権を奪還したタリバン政権が、2022年4月にケシ栽培を禁止し、取り締まりを行ったためである。アフガニスタンでの栽培は、世界全体でのケシ供給の80%を占めていたため、ヘロインなどのオピオイド系麻薬の密売、使用が世界で減少するという予測もある。しかし一方で、フェンタニルなどの合成オピオイドなどの代替品が急速に広まる恐れも指摘されている。さらに、タイ、ラオス、ミャンマーの「黄金の三角地帯」では、アフガニスタンに代わってケシの栽培が急増しているのが現状である。特にミャンマーでは、2022年で33%も増加している。また、ケシ栽培を生活基盤としていた農民たちは、収入源を失って困窮に陥っている。実際に、ケシ栽培の禁止によって失った収入は10億米ドル以上にものぼるとされており、代替である小麦栽培で得られる収入では到底まかないきれていない状況だ。また、ケシ栽培が禁止されたアフガニスタンでは、メタンフェタミン(覚醒剤)の生産が急増している。
報道量
朝日新聞:0記事/0字
毎日新聞:1記事/852字
読売新聞:0記事/0字

アフガニスタンのケシ畑(写真:United Nations Photo /Flickr [CC BY-NC-ND 2.0])
2023年の10大ニュースを振り返ると、気候変動などの環境にまつわる問題や、水や食料不足、武力紛争といった人道危機に関する問題などが多くランク入りした。どのニュースも、たくさんの人に影響を与えている大きな出来事だが、日本のメディアではほとんど取り上げられていない。
また、候補に上がったものの、10位以内には入らなかったものも含めて見渡しても、やはり気候変動問題や食料問題が特に深刻化しているように思われる。たとえば、気候変動問題においては、南極での海氷減少やスイスでの氷河激減などにも注目した。また、麻薬関連については、アフガニスタンのケシ栽培の変化に加え、コロンビアでのコカ栽培の増加や中東アフリカでのカプタゴン(覚醒剤)流通の増加も見られた。他には、長年改善が見られないジェンダー問題についても、世界の9割の人々が女性に対してジェンダーバイアスを持つという調査結果が発表されたことや、南アジアの女児の婚姻が世界最多という状況を、重大なニュースとして捉えた。
GNVでは、2024年も引き続き「報道されない」世界各地の重大な出来事について注目し、読者の方々にお届けしていく。
※1 ランキングの選出にあたっては、出来事・現象の報道量、及ぼす影響の大きさ、2023年での変化の規模など、複数の基準に則り評価を行った。また、2023年以前より続いている出来事や現象であっても、2023年に明らかになった事柄については2023年に起きたニュースと同様にランクインさせている。
具体的な決め方は以下の通りである。世界を6つの地域(①東・南・中央アジア、②東南アジア・太平洋・インド洋、③中東・北アフリカ、④サハラ以南アフリカ、⑤ヨーロッパ、⑥南北アメリカ)に分け、それぞれの地域で起こった重大と考えられる出来事・現象で、日本国内において報道量の少なかったものを4件ずつ、さらに地域に限定されないグローバルな出来事・現象を6件、計30件ピックアップした。
それぞれの出来事・現象に対して、(1)報道量の少なさ、(2)影響を受ける人数と影響の度合い、(3)政治・経済・社会・安全保障などのシステムへの影響度、(4)越境性、(5)新鮮度という5つの基準について、それぞれ3点満点で点数をつけた。特に、注目されていない事柄を重要視するランキングであるため、(1)報道量の少なさに関しては比重を倍にした。その結果をもとに候補に上がった30件から10件に絞り、編集会議で協議して順位を決定した。なお、報道量は2023年1月1日から2022年12月15日までを集計したものである。
※2 報道量を調べる際には、朝日新聞・毎日新聞・読売新聞3社のオンラインデータベース(朝日新聞:朝日新聞クロスサーチ、毎日新聞:マイ索、読売新聞:ヨミダス歴史館)を使用した。全国版と地域版の東京の朝刊及び夕刊を対象とし、見出しのみならず本文にも着目した。
※3 ゴールに対して、具体的な目標をターゲットで示している。ターゲット1「2030年までに、すべての女子と男子が、適切かつ効果的な学習成果につながる、公平かつ質の高い無料の初等教育および中等教育を完了できるようにする。」
※4 クルディスタン地域とは、イラク北部のクルド系住民が中心となっている自治地域。
※5 損失と損害とは、気候変動の避けられない影響による被害のこと。インフラの破壊や作物数量の減少など、被害が定量化できる「経済的損失と損害」と、文化や生活様式の喪失など被害の規模を計りにくい「非経済的損失と損害」の大きく二つに分けられ、特に後者は修復不可能になる傾向が高い。
※6 G5サヘル同盟とは、マリ、ブルキナファソ、ニジェール、チャド、モーリタニアの5カ国で2014年に構成された、サヘル地域の治安維持のための取り決め。ただし、2022年に同盟を離脱したマリに続き、2023年にブルキナファソとニジェールが離脱したため、G5は解消を検討している。
(修正:第1位のタイトルを「 G20、化石燃料への補助金が4倍に急増」から「G20諸国で化石燃料に対する補助金が4倍に急増」に変更しました。(2023年12月28日))
ライター:Yuna Nakahigashi

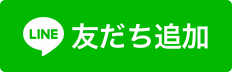









日テレより:
https://news.ntv.co.jp/category/international/0bb8233180054717b51023c2118a36de
「第3位 世界の教師不足が4,400万人に」がまず目に留まった。国内での教員不足が叫ばれて久しいが、原因は地域によって異なることはいえ、世界でも同様の問題があるとは知らなかった。またあえてポジティブサイドに目をやると、2016年からの数年間で教員が2500万人増加している。これにも地域差があるのか、そこではどういった背景で教師が増えているのか、国内にその構造から転用できる部分が無いかなど気になる点がある。
今年で大学を卒業するが、社会人になっても毎年この記事を読みたいと思った。
日テレ以外の各社もこれを取り上げるべきだと思いました。
こんな感じで順位がついているのは見やすいですね。上位にランクインしているニュースでさえ全く聞いたことがなかったです。なぜ報道されないのでしょうか、、、
全く聞いたことのない記事が多くあり勉強になりました!報道されていない割に世界に影響を大きく与えるニュースばかりで驚きです。もっとたくさんの人が知ってほしいことだと思いました。
日本の大手メディアはこれだけ重要な世界の出来事をここまで無視するとは・・・
本当にひどい話です。
世界がほとんど見えていませんね。
こういう記事を読むと、独立系メディアの役割はとても重要だと確信しますし、大手メディアに見習ってほしいです。
頑張ってください!
聞いたことの無いニュースが沢山ありました。
世界に大きく影響を与える出来事ばかりなのに、なぜ今まで注目されていなかったのでしょうか?不思議でなりません。
サウジアラビアのニュース、怖すぎる。
こんなのはなんで報道されない?
日本がサウジの石油に頼ってるから?
イスラエル・ガザへの過熱した報道は、世界へのゆがんだ理解を生みかねませんね。
本当に伝えるべきニュースは何なのか、テレビ・新聞はじめ各報道機関に知ってもらいたい
リソース不足は言い訳に出来ないはずです
毎年楽しみにしてるランキングです。
これからも頑張って下さい!
大塚製薬もひどいね。報道しないと国民が知ることもないね。製薬会社がマスコミのスポンサーになってるから報道しないのか。
読売新聞もLINE NEWSも「海外」の10大ニュースに「チャールズ英国王戴冠式」が入っていました。
また、読売新聞にはラブビーW杯、LINE NEWSにはハリウッドのストライキもランクインしました。
エンタメも重大ニュースのようですね。
アフガニスタンでケシ栽培が減ったのはすごいことだと思う
なぜメディアはタリバン政権のこういった面を取り上げないのか