パナマ文書の報道開始から約5年が経過した2021年10月3日、タックスヘイブン(租税回避地)を利用した金融取引を記したパンドラ文書(※1)が国際ジャーナリスト調査連合(ICIJ) により暴露された。2016年に発表されたパナマ文書の規模を上回り、過去最大のリークかつ最大規模の調査報道となった今回の発表で、世界の政治家や大富豪たちが隠れて保有していた富が明るみに出たのである。多数の国の首脳陣や、日本を含む各国の有名人も文書に名前が記載されている。富める者はますます富み、社会における不平等を助長している現在の経済システムに大きな一石を投じるきっかけとなったはずの本事件は、日本ではどのように報道されたのであろうか。今回の記事では、パンドラ文書とは何かを詳しく説明するとともに、比較的報道量があったとされるパナマ文書と比較しながら、パンドラ文書がどのように報道されたのかを探る。
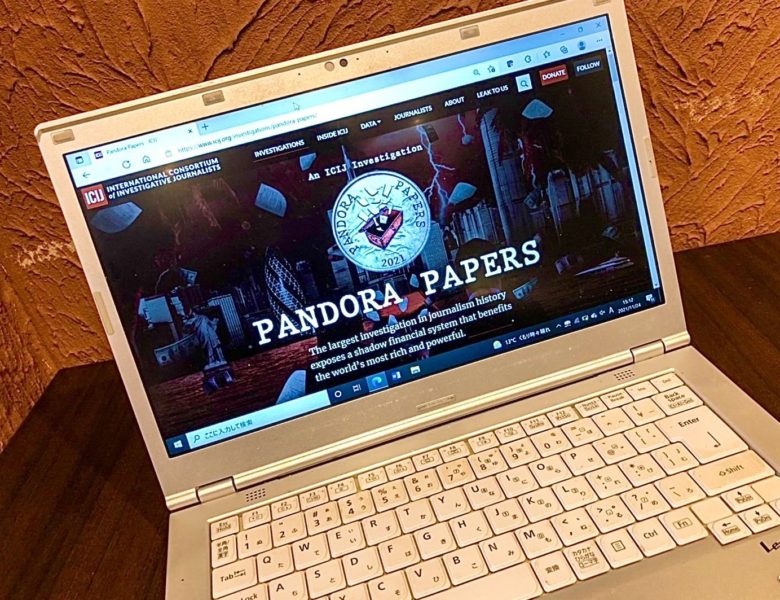
撮影:Anna Netsu
タックスヘイブン問題と過去のリーク
そもそもタックスヘイブンとは何か。過去のGNVの記事でも詳しく説明しているが、タックスヘイブンまたはオフショア金融センターとは一般に、外国企業や法人に対する法人税をきわめて低く、またはゼロに設定している国や地域のことを指す。タックスヘイブンの特徴の一つに、情報の秘匿性が挙げられる。タックスヘイブンで設立された企業とその所有者に関する情報公開は制限されているのだ。そこで世界各国からの個人や企業が租税回避や脱税を目的に利用されている。租税関連以外にも、追跡から逃れて資金を隠したり、金融などに関する規制や手続きから逃れたり、マネーロンダリング等の犯罪行為を行ったりすることが可能となる。ある試算によれば、世界の経済活動のおよそ10%がタックスヘイブンに移転されていると言われている。
タックスヘイブンの利用にあたって必要な要素の一つとして、ペーパーカンパニー、信託会社や基金が挙げられる。ペーパーカンパニーとは法人として登録はされているものの、事業活動の実態が伴わない会社のことを指す。企業はタックスヘイブンにペーパーカンパニーを設立させ、実際の所有者の存在を隠し、利益を移転させる。こうすることで、課税回避や規制逃れ、マネーロンダリング等の犯罪、そして資産を隠すことが可能となる。また、利用する個人や企業は基金をタックスヘイブンに設置したり、信託会社を利用したりして、財産を保管するという仕組みもある。加えて、タックスヘイブンのインフラを提供しているのは法律事務所や会計事務所、大手銀行等なのである。
ではなぜタックスヘイブンは問題になるのだろうか。大きな問題の一つは、社会全体を豊かにするために課せられるはずの税金が、平等に徴収されなくなるからである。タックスヘイブンを利用することによって資産家たちや法人は何億米ドル相当にものぼる税金の支払い義務から逃れている。2016年には世界各国で本来なら得られるはずの税収2千億米ドル以上が徴収されなかったという研究結果が発表されている。では資産家たちが支払いから逃れた税金は誰が払うのだろうか。それは、大きな資産を持たない残りの多くの市民なのである。タックスヘイブンを利用した租税逃れはそもそも、大きな資産を保有する富豪にしか利用できない仕組みであるのだ。

タックスヘイブンの一つとして有名なモナコの港(写真:Mike McBey / Flickr [CC BY 2.0])
しかも、情報の秘匿性という特徴ゆえに、資産がタックスヘイブンを利用して隠されてしまうと、資産家たちが適切な税金を支払っているのかどうかさえ、第三者がチェックできなくなってしまう。この秘匿性があるためにタックスヘイブンという問題自体が見えてこず、租税逃れが発生しているのかどうかも知るのが難しくなっている。また、こうしたタックスヘイブン問題で特に大きな被害を受けるのは低所得国である。経済基盤が安定していない低所得国ほど、道路や学校、病院といったインフラ設備や、そこで働く教師、医療従事者等公務員の重要性が高まる。にもかかわらず、公共出費を賄うのに必要不可欠な税金が平等に徴収されなくなってしまうのだ。法整備やチェック機能が比較的に脆弱な低所得国では特に、外資系企業がタックスヘイブンの仕組みを用いて、不法資本流出をさせているケースが特に激しいのだ。
問題になるのは税徴収の面だけではない。タックスヘイブンを利用すれば、一般の法人や個人には課せられるはずの規制等からも逃れることができてしまう。例えば、労働法関連の規制を逃れ、賃金や保障のレベルを下げていたケースが報告されている。また、銀行が情報の不透明性を利用して規制を回避し、本来であれば高リスクゆえに禁じられているような投資を行うこともある。こうして、富める者とそうでない者の間の不平等がますます深化しているのだ。
内部告発者からのデータをもとに、タックスヘイブンを使った取引の暴露は過去にも度々発生しており、その多くを冒頭に紹介したICIJが行っている。以下にその主要なものを紹介していく。
最初に行われた調査はオフショア・リークスと呼ばれた。これは2012年11月と2013年4月の2度にわたってICIJが暴露したもので、ポートカリス・トラスト・ネットとコモンウェルス信託会社から流出したデータである。次に2014年1月にもオフショア・リークスの一環として、中国、台湾、香港の、オフショア企業を保有する人物の名前が公開された。2014年12月のルクセンブルク・リークス(ルクス・リークス)では、大手会計事務所のプライス・ウォーターハウス・クーパースとルクセンブルクの税務当局が行った課税優遇措置が明らかになっている。また2015年2月のスイス・リークスでは英金融大手HSBCが行った租税回避・脱税のほう助を行っていたことがわかった。
2016年4月には、パナマの法律事務所モサック・フォンセカから情報が流出し、当時最大規模のリークであったパナマ文書がについての報道が開始された。 2016年9月には、カリブ海に位置するタックスヘイブンであるバハマにおける法人に関する情報を記したバハマ文書 についてもされている。2017年11月にはパラダイス文書にて、大手法律事務所アップルビーから流出した取引が明らかになった。パンドラ文書以前の最新のリークは2020年9月のフィンセン文書で、アメリカの金融犯罪取締ネットワーク部局(FinCEN)に提出された不信行為報告書が流出したことにより明らかとなった。世界の大手銀行がマネーロンダリングや金融犯罪を野放しにしていた事実が明るみに出ている。
パンドラ文書とは
次に、最新のリークであるパンドラ文書とは何かを説明していく。パンドラ文書は5年前のパナマ文書の規模を上回る過去最大のリークとなっており、文書や画像、メール等を含む1,190万件以上、2.94テラバイトもの大きさのデータである。14の会計事務所、法律事務所、コンサルティング会社等仲介を担う機関から流出したデータであり、ICIJが150の報道機関に所属する600人以上のジャーナリストたちの協力のもと、2年の歳月をかけて情報の分析を行った。パンドラ文書は35人の現職又は過去の首脳、91の国や地域における330人以上の政治家や官僚、そして資産家や法人、芸能人、犯罪者たちによるタックスヘイブンを利用した取引を明らかにしたものであり、文書に記載のあったペーパーカンパニーの数は29,000以上に及ぶ。

パンドラ文書に記載のあった首脳陣の名前として、ヨルダンの国王であるアブドゥラ2世・ビン・アル=フセイン氏、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領、ケニアのウフル・ケニヤッタ大統領、エクアドルのギレルモ・ラッソ大統領、チェコのアンドレイ・バビシュ首相、チリのセバスティアン・ピニェラ大統領が挙げられる。他にも、イギリスのトニー・ブレア元首相、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領の側近、アゼルバイジャンのイルハム・アリエフ大統領の子息などの名前が記載された。著名人ではリンゴ・スター氏やエルトン・ジョン氏といったミュージシャンや、モデルのクラウディア・シファー氏の名前も見られる。また、日本では孫正義氏(ソフトバンクグループ会長兼社長)、平田竹男氏(元内閣官房東京五輪パラリンピック推進本部事務局長)、安田隆夫氏(ドン・キホーテ創業者)、原丈人氏(未来トラスト会長)らの名前が挙がっている。
パンドラ文書による影響を受けた派生事件が1カ月もたたないうちにいくつか発生している。文書に名前が挙がったチェコのバビシュ首相率いる与党は下院選において敗北し、政権交代に繋がった。チリ議会下院では、ピニェラ大統領の弾劾が可決された。結局与党が過半数を占める上院にて弾劾案は否決されたが、パンドラ文書の大きな派生事件の一つと言えるだろう。エクアドルのラッソ大統領は脱税の疑いで調査されることが決定している。
またアメリカでは、パンドラ文書の影響により、国内に資産を移転させようとしている国外顧客がいないかどうか、信託会社、法律事務所等の仲介業者に強制的に調査させるための法案が議会に提出されている。加えて欧州議会では、パンドラ文書により明らかとなった不正行為について調査を進めるための決議、そして現行法を正確に履行していない欧州連合(EU)加盟国に対して欧州委員会が法的措置をとるための決議が採択された。また、政界以外にもいくつか動きが見られた。美術商のダグラス・ラッチフォード氏に関する情報が文書に記載された結果、カンボジアの古代遺跡から略奪された文化財が、タックスヘイブンの信託の管理下に移されていたことが発覚し、カンボジアへ返還されることが決定した。今後もパンドラ文書の影響を受けた社会事件が発生することが予想されるだろう。
パンドラ文書の報道比較・分析
世界における格差を助長させる巨大な国際問題であるタックスヘイブンに関する、過去最大規模のリークであり、様々な付随事件も発生しているパンドラ文書関連の出来事は、日本ではどのように報道されたのだろうか。過去に比較的報道されたパナマ文書関連の報道と比較して見ていこう。今回は、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞3社における、パナマ文書・パンドラ文書それぞれの報道開始後30日間(※2)に掲載された記事を対象とする。記事のうち、「パンドラ文書」・「パナマ文書」か「租税回避地」の単語が含まれているものを検索し、そのうちパンドラ文書・パナマ文書に関す言及が2文以上のものを抽出した(※3)。また、各文書により発生した派生事件についてもカウントに入れている。
カウントの結果、パナマ文書では、記事数が朝日新聞49件、毎日新聞59件、読売新聞61件に対し、パンドラ文書では、朝日新聞11件、毎日新聞4件、読売新聞1件と、大幅に報道量が減少していることがわかった。報道自体だけでなく、文書やタックスヘイブン問題に対する解説を行う記事や、社説にも差がでている。パナマ文書では解説記事が朝日新聞1件、毎日新聞2件、読売新聞5件であったのに対しパンドラ文書では朝日新聞1件、毎日新聞0件、読売新聞0件であった。社説に関しても、パナマ文書では朝日新聞2件、毎日新聞2件、読売新聞1件である一方、パンドラ文書ではどの新聞社も記事数0件であった。
パナマ文書報道で特徴的であったのは、国際的な反応と関連した報道である。パナマ文書発表の11日後である2016年4月14日に開催されたG20財務省・中央銀行総裁会議ではタックスヘイブン問題に対する議論がなされ、朝日新聞4件、毎日新聞6件、読売新聞5件とそれなりの数の記事が掲載されている。パナマ文書を受け、経済協力開発機構(OECD)は2016年4月13日に各国税務当局による緊急会合を開いており、こちらと関連付けた記事も、朝日新聞4件、毎日新聞3件、読売新聞6件とカウントされた。
パンドラ文書の報道が開始した時期には大きな経済会議はなかったものの、OECDで最低法人税率を15%とする合意が136ヵ国との間で2021年10月8日に取り決められた。課税逃れを防ぐための案である今回の合意はしかし、パンドラ文書に関連付ける報道はほとんどなかった。朝日新聞は一面にて最低法人税率のニュースを取り上げたがパンドラ文書への言及はせず、社会面にて、日本国内でパンドラ文書に名前のあった人物・会社に関する記事の中で、最低法人税率の合意について言及した。毎日新聞は総合面にて最低法人税率に言及するがパンドラ文書には触れず、また読売新聞も最低法人税率のニュースが社説のトピックになっていたが、パンドラ文書が言及されることはなかった。
パンドラ文書に名前の載った日本の有名人に関しても、かなり報道量が少ない結果となっている。日本の著名人に言及したのは朝日新聞の1件のみであり、言及があったのは孫正義氏、平田竹男氏、原丈人氏の3人であった。孫氏はタックスヘイブンに子会社を、平田氏と原氏は法人を設立させていたことが明らかになったが、3名全員が租税回避目的で設立させたわけではないという旨の説明をしている様子を記載しただけであり、3名の経済活動に対する深堀はなかった。毎日新聞、読売新聞において、文書に名前の載った日本の著名人の言及は見られなかった。

EUで開かれたパナマ文書に関する公聴会、ジャーナリストとともに(写真:The Left / Flickr [CC BY-NC-ND 2.0])
それぞれの文書に関連した派生事件に対する報道にも差が出ている。パナマ文書において例えば、アイスランドのシグムンドゥル・ダーヴィド・グンロイグソン元首相はパナマ文書がきっかけとなり辞職したが、このニュースは朝日新聞で3件、毎日新聞1件、読売新聞では4件報道された。また、イギリスのキャメロン元首相関連で、議会での追及や支持率低下など、パナマ文書によって派生した出来事は、朝日新聞1件、毎日新聞5件、読売新聞7件報道された。他にもアルゼンチン大統領(朝日1件)や欧州サッカー連盟(朝日1件、毎日1件、読売1件)、大手銀行(毎日2件)、法律事務所(毎日1件、読売2件)、金融機関(朝日1件)に対する捜査が行われた類のニュースも複数回なされた。一方パンドラ文書においては、チェコ下院選における与党敗北のニュースが朝日新聞で1件、毎日新聞で1件され、カンボジア文化財返還のニュースが朝日新聞で1件報道されただけとなっている。
また新聞以外のメディア媒体でも、パンドラ文書が報道されていないという傾向に変わりはない。テレビニュースに関して、NHK総合で月曜から金曜の21時から1時間放送されているニュースウォッチ9で、パンドラ文書の報道開始から10日間の放送を調べたところ、パンドラ文書を取り上げているものは0件であった。また、チャットアプリであるLINEが運営している、多くの報道機関からニュースを集めて発信するLINE NEWSのうち、厳選されて1日24記事選出されるLINE NEWS DIGESTでもパンドラ文書への言及は0件であった。さらにオンラインメディアであるハフポストにて「タックスヘイブン」のタグの付いた記事を検索したところ18件がヒットしたが、そのうちパンドラ文書に言及しているものは0件であった。
パンドラ文書はなぜ報道されないのか?
社会的影響力が大きかったはずのパンドラ文書は、なぜこれほどまで報道されなかったのだろうか。考えられるいくつかの理由を見ていこう。まず、これはパンドラ文書・パナマ文書に共通して言えることになるが、そもそもタックスヘイブン問題が報道されにくいということが挙げられる。なぜなら、タックスヘイブンのような、長年続く仕組み・システムに関するトピックは、単発的に発生した事件等よりも、報道として注目を集めにくいという特徴があるからだ。また、先述の情報の秘匿性も、取材のしにくさを助長する。だからこそICIJのような機関が数年をかけて情報収集をし、パナマ文書、パンドラ文書のような情報の公開が可能となっているのである。

ノートをとる記者(写真:Roger H. Goun / Wikimedia Commons [CC BY 2.0])
次に、パナマ文書と比較した際に、パンドラ文書が報道されなかった理由について、いくつか挙げていく。この点については、そもそも日本だけでなく世界で、パンドラ文書はパナマ文書より報道量が少なかった(※4)。ではなぜ世界的にパンドラ文書とパナマ文書で報道量に差がでたのだろうか。考えられる理由をいくつか探ってみよう。
まず、文書に記載のあった政治家たちの知名度の違いという部分が指摘できる。パナマ文書では、中国の習近平国家主席の姉の夫や、ロシアのプーチン大統領の親友、そして当時現職のイギリスのデーヴィッド・キャメロン首相といった、普段国際政治の舞台でよく注目が集まる政治家たちの名が記載された。しかしながらパンドラ文書では、ロシアプーチン氏周辺人物の名前は挙がったが、他の国々の首脳陣は、普段の報道ではあまり取り上げられない国の人々ばかりである。普段から、報道対象として注目されている国か否かが、今回の違いにも影響を与えたと考えられる。
他に考えられる理由について、ICIJの記者であるシッラ・アレッチ氏に尋ねてみた。彼女は、パナマ文書の際にはメディア映えするような派生事件が多数発生し、それらに対する世間のリアクションも大きかったことを指摘した。例えばアイスランドのケースを見てみると、パナマ文書に名前が記載されたグンロイグソン元首相は、タックスヘイブン問題に関しインタビューを受けた際、途中でカメラに背を向けて逃げるように立ち去る場面が大きく報道されている。こうした首相の姿も含め、アイスランドのような高度に民主的な国では、首相に裏切られたと感じた民衆の怒りが大きかったと彼女は話す。実際、議会前を埋め尽くすほどの大規模なデモも発生しており、またそうしたデモの様子もメディアによって大きく報道されている。他にも、パナマ文書報道開始の数日後にアメリカのバラク・オバマ元大統領が会見を開き、タックスヘイブン問題への対処を呼び掛けたことも、注目を集める要因となった出来事だとアレッチ氏は指摘する。

アイスランドの首都レイキャビクでのデモの様子(写真:Art Bicnick / Flickr [CC BY-NC-SA 2.0])
一方でパンドラ文書では、こうした社会からのリアクションがあまり見られなかったと彼女は言う。例えば、政府関係者としてパンドラ文書に名前が挙がったチェコのバビシュ首相に関して、パンドラ文書の影響を受けて首相率いる与党が下院選で敗北を喫しはしたが、大きなデモ等は発生してはいない。また、王国であるヨルダンでは、政府が直接的・間接的に国内メディアの多くを保有しており、パンドラ文書に関する報道がシャットアウトされていた。よって、そもそも民衆がパンドラ文書のような情報にアクセスする術を持たず、それ故にヨルダン国内でパンドラ文書に対するリアクションも発生しないという点についてアレッチ氏は言及している。
さらに、GNVは日本の国際報道が普段から欧米メディアを追随していることを指摘してきた。パナマ文書報道、パンドラ文書報道においても日本の報道はこの特徴をよく表していた。上述のように、欧米で反響の大きかったパナマ文書は日本国内でも大きく取り上げられ、反響の少なかったパンドラ文書に関する報道が少ないのだ。
朝日新聞の記者であり、タックスヘイブン問題の報道に多く携わっている奥山俊宏氏は、パナマ文書の際は文書それ自体ではなく、反響に対する記事が多く書かれたために報道量が多かったのではないかと述べている。彼によれば、パナマ文書に関する報道を始めた当初は日本国内ではさほど大きな反響は見られなかったが、3、4日ほどたつと欧米の反応が輸入される形で、日本国内でも大きな反応が見られるようになったと感じているそうだ。ここでの反応とは、国外のニュースをチェックする人々のツイッターでの投稿などインターネット上の書き込みや新聞社の海外特派員が現地から送ってくる記事の量などを指していると彼は言う。またオバマ氏の記者会見のように、アメリカ大統領の動きがあるかないかも、反響の大きさに影響を与えていることを奥山氏は指摘している。実際朝日新聞において、両文書について報道を開始した後すぐの3日間の報道量を見てみると、パナマ文書よりもパンドラ文書関連の報道の方がより多かったと奥山氏は振り返る。しかしパナマ文書の時は報道に対する世の中の反響が大きかったために、4日目以降報道量が逆転していったのではないかと彼は述べている。

パンドラ文書に名前が記載されたチェコのアンドレイ・バビシュ首相(写真:ALDE Party / Flickr [CC BY-NC 2.0])
また、孫氏など日本の社会にも大きな影響力のある人物の名前が記載されたのにもかかわらず、パンドラ文書が大きく報道されなかったという指摘についてもお聞きした。奥山氏は、文書に名前が載った以上の情報にアクセスできなければ、「税逃れをしていないという先方(文書に名前が載った人物)の抗弁を崩すことができない」ため、文書に名前があるだけでは大きく報道することはできないと述べている。以前は日本の法律の下で、所得額の大きい個人の納税額が公表されていたが、十数年前に公表制度がなくなったため個人の納税額を知ることはできなくなったという。そのため、税を払っているか払っていないかを確認することができない状況が発生していると奥山氏は指摘する。
しかし、パンドラ文書は日本での租税問題だけではなく、グローバルなレベルでの巨大な問題でもある。その側面からの報道が少なかったことに対して、日本の新聞社として、パンドラ文書をグローバルな問題としてではなく、日本国内からの視点からとらえている傾向があるのではないだろうか。実際に奥山氏は、「日本の報道機関として最も大切なのは日本の国内で日本の国内法に触れるような不正とか税逃れが行われていないか(をチェックする)ということ」であり、日本のローカルな視点に立脚し、かつ、グローバルに問題をとらえるのが重要だ、と述べている。その上で、奥山氏は「国際世論の圧力がないとタックスヘイブン対策は進まない」「日本は国際社会で対策の仕組みづくりを主導すべきだ」と呼びかける解説記事を出したことは見落とされるべきではないと指摘した。
上述の、3つの新聞社における報道量を比較したときに、朝日新聞の報道量が比較的多いことがわかるが、これは朝日新聞がICIJと提携関係を結んでおり、ICIJ提供の記事にアクセスしやすいことが背景にあると考えられる。よって今回は朝日新聞が他社よりも先に多くの情報を報道しやすい状況であったと言える。しかしながら日本の報道機関の姿勢として、他社のスクープを追って報道するという動きが多くないという特徴をアレッチ氏は挙げている。例えば、欧米メディアは他社が先に出したスクープについて、他社名を引用し追随して報道を行うことがある。一方で、日本のメディアは他社の名前を引き出し、追って記事を出すことをあまりしないとアレッチ氏は言う。それ故、例えば過去のリーク(フィンセン文書)の際は朝日新聞ではなくICIJの方に、文書関連の情報について問い合わせることがあったが、パンドラ文書ではそれもなかったと彼女は振り返っている。

インタビューの様子(写真:Kristin Wolff / Flickr [CC BY 2.0])
まとめ
パンドラ文書に触れたことで、現行の経済システムの陰で動く不平等な世界という莫大な問題を私たちは目撃することとなった。今回は、いかに富める者が制度の穴をついて利益を得てきていたかがわかる、数少ない機会の一つだったのである。そしてこのことは、世界中の多くのジャーナリストたちのおかげで可能となった。しかしながら、これほど重要な問題を、果たしてどれだけの人が把握することができているのだろうか。
タックスヘイブンを使い、権力者や大富豪が富を隠し、税金や規制を逃れている現状は、法の支配や民主主義の原則にとって、大きな課題の一つであるはずだ。タックスヘイブン問題は日本にとっても対処すべき点の一つであることに変わりはない。タックスヘイブンを、日本国内のみの視点から捉えるのではなく、日本を含む世界にとっての大きな課題として問題提起していくことが、報道機関に求められる大きな役割の一つではないのだろうか。
【訂正(2021年11月26日):誤解を避けるため、取材協力者からの聞き取りに関連する部分で1箇所の文を追加した。その他に、パンドラ文書に関する朝日新聞の解説記事の数について、ICIJに関する説明について、2箇所で訂正を行った。】
※1 「さまざまな災いを引き起こす原因となるもののたとえ(故事成語を知る辞典より)」を意味する「パンドラの箱」からきている。
※2 パナマ文書は2016年4月3日から2016年5月2日、パンドラ文書は2021年10月3日から2021年11月1日の間に掲載された記事数をカウントしている。
※3 なお、パナマ文書・パンドラ文書とその関連事件に対する言及が一文のみのものは、十分に情報を伝える役割を果たしていないとしてカウントしない。
※4 アメリカの新聞紙ニューヨークタイムズで、「パナマ文書」・「パンドラ文書」のキーワード検索でヒットした記事数をカウントしたところ、パナマ文書は55記事、パンドラ文書は22記事となっている。
ライター:Anna Netsu
グラフィック:Minami Ono
取材協力:シッラ・アレッチ氏(Scilla Alecci)(ICIJ)、奥山俊宏氏(朝日新聞)










日本のマスメディアはパンドラ文書とかの世界的な税制問題を全然報じないので、こういった問題が軽視されてしまう。
よく、課税の累進性を強くすると富裕層が海外に逃げると反対する人がいるけど、現状でも物理的じゃないけど、仕組みを使って逃げている人はたくさんいる。彼らにきちんと課税する仕組みが大事だと思う。
あと、いい文章だ
1つの記事の中で学ぶことが多く、すごく面白かったです。グラフィックもわかりやすいし、いろんな方の視点を取り入れていて濃い内容だと感じました。
実はコレ
株式のインサイダー取引の舞台だということが報じられていません。
実はコレ
株式のインサイダー取引の舞台だということが報じられていません。