2024年12月2日、気候変動における各国政府の義務と違反した場合の法的責任について国際司法裁判所(ICJ)の意見を求める審議の一環として公聴会が開始された。この公聴会は約2週間にわたり、過去最多となる96の国と11の地域的組織が意見陳述を行った。これは気候変動における国家の法的な責任を問う初めての試みであり、世界中の関心を集めた環境問題における大きな一歩である。
この動きを主導したのは南太平洋に浮かぶ小さな島国バヌアツである。バヌアツを含めた太平洋諸国では、気候変動の原因である温室効果ガス排出量は極わずかであるにもかかわらず、気候変動の影響が深刻であり国家と人々の生存が脅かされている。バヌアツは長年の間太平洋諸国を率いて気候変動問題に取り組んできた。
本記事では、太平洋諸島のおかれている現状と今回のICJでの協議に至るまでの一連の動きを振り返りたい。
(この出来事は「GNV 2024年潜んだ世界の10大ニュース」にて第6位にも選出しされている。)

ICJでの公聴会(写真:UN Photo/ICJ-CIJ/Frank van Beek [Fair use])
太平洋諸島における気候変動の現状
太平洋諸島は太平洋に点在する島々であり、島の数はあわせて4,000以上にも及ぶ。各島には長年にわたり先住民が移住・定住してきた。16世紀以降ヨーロッパ諸国、アメリカ、オーストラリアや日本などによる植民地支配を経験し、1962年にサモアの独立に続いて複数の国が独立を果たした。しかし、太平洋諸島にはまだ独立していない、ヨーロッパ諸国などが所有したままの島が多数存在する。詳しくはGNV記事を参照いただきたい。
各国内を見てみると、人口約1,000万人(2025)のパプアニューギニアから1,800人(2025)程度のニウエ(※1)まで人口や面積は国・地域によって様々である。ほとんどの国・地域の経済が脆弱なのは、国土が広大な地域に散らばり、市場が小さく、国際市場からも地理的に離れており産業が発達しにくいからである。そのため旧宗主国を中心とした他国からの援助等に依存している傾向がある。その代わり、他国と自由連合協定などを結んで、経済面以外にもその国から大きな影響力を受けている国もある。
太平洋諸島で気候変動による存続危機が叫ばれるようになって久しい。海洋に起きているいくつもの異常な現象は気候変動の複雑さと深刻さを物語る。海面上昇の加速、海洋の温暖化、酸性化という3つの打撃は島土面積の小さい島々にとっては致命的なものである。
国連の報告によると、1993年から2023年までの太平洋の平均海面上昇幅は15cmに及び、今後世界の気温が産業革命前と比較して1.5℃~3.0℃上昇すると、太平洋では最大50~68cmの海面上昇に直面する可能性があるという。その被害がすでに各地で見られており、例えばフィジーのバヌアレブ島では海面上昇と海岸浸食による洪水のため、内陸部への移転を余儀なくされたコミュニティもある。
海水温上昇や酸性化は生態系の変化をもたらす。例えば、2023年以降世界的なサンゴの白化現象が再び確認されているという研究もある。サンゴの白化は、特にサンゴの生息圏で生活している人々にとっては経済や食料安全など広い意味で影響力をもつものである。

2015年バヌアツでのサイクロンの被害(写真:United Nations Development Programme / Flickr[CC BY-NC-ND 2.0])
また、上の3つ打撃に加え極端な気象現象の増加も問題であり、高潮による洪水や激しいサイクロンなどで大きな被害を受けている国・地域も少なくない。2023年3月にバヌアツで連続して発生したサイイクロン・ジュディとサイクロン・ケビンにより、国民の66%が被害を受け、総被害額は4.3億米ドルに及んだとされている。
このような気候危機は太平洋地域に限らず地球全体で起きていることではあるが、太平洋での被害がすでに深刻なレベルに達しているのは明らかである。
今までの気候変動対策
こうした脅威に対抗すべく、太平洋諸国・地域は地域的な協調を強めてきた。太平洋諸島フォーラム(PIF)はその一環である。気候変動は災害リスクの増大だけでなく政治や経済発展にも深刻な影響を与える。PIFは政治・経済・安全保障などの幅広い分野における対話・地域協力の場として機能しており、気候変動対策の分野では画期的な合意に至っている。「太平洋における強靭な開発のための枠組み(FRDP)2017-2030」はその一例である。PIFについてはGNVの記事もあるので参照いただきたい。
しかしながら、資金不足が足かせとなっている状態も長い間変わっていない。気候関連の国際基金などもあるものの、構造上の障害により太平洋地域が十分な資金にアクセスする機会は欠如している。

ツバルでの海岸整備プロジェクト(写真:UNDP Climate / Flickr[CC BY-NC 2.0])
現在、国家間おいて気候変動問題に関わるルールの基準となっているものの1つとしてパリ協定が挙げられる。2015年の第21回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21)で採択された協定で、低所得国を含めるすべての参加国に温室効果ガス排出削減の努力を求める枠組みとして画期的と言われたが、あくまで努力目標・奨励にとどまり進捗状況の報告以外に義務は科されていない。パリ協定に基づいてさまざまな気候変動対策が行われているが、法的拘束力を持たないためその成果は不十分である。
ここで、気候変動対策において重要な考え方のである「緩和(Mitigation)」「適応(Adaptation)」「損失と損害(Loss & Damage)」という3つの概念に触れておきたい。「緩和」とは、温室効果ガス排出削減など気候変動の原因に対する対策であり、「適応」とは洪水や海面上昇に備えて防潮堤を建設するなど、気候危機の不可避な影響に対して講じるものを指す。「損失と損害」とは、このような「緩和・適応」対策があっても起きてしまった悪影響に対して講じる対策のことである。「損失と損害」という概念は、公正さ・公平さに深く結びつくものである。なぜなら、世界で気候変動に脆弱な国の多くが、温室効果ガスの排出量が最も少ない国だからだ。この言葉は2013年COP19にて初めて正式に使われ、それ以来関心が高まっている。太平洋諸国もこの概念を重要視しており、2022年のCOP27においては優先して「損失と損害」のための基金の設立を強く提唱していた。その結果、COP27では初めての「損失と損害」に対する基金が設立された。
2024年11月にアゼルバイジャン・バクーにてCOP29が開催された。議論は難航し日程を延長して議論が行われたが、結果として、気候資金に関して前進があった。気候変動対策資金としての拠出について、2035年までに年間3,000億米ドルを目標額にする妥協案で合意した。これは気候変動に脆弱な低所得国側の求めた1.3兆米ドルには遠く及ばないものの、現行の目標の3倍に相当する。他にも、国際的な炭素クレジット取引に関するルール決定やエネルギー関連での合意、ジェンダーと気候変動についての議論が取り上げられるなど、一定の成果を残した。
しかしながら、今回も具体的進展は不十分だとする声のほうが大きかった。これまでの進め方の根底にあった「善意」としての協力ではなく、法的効力をもって義務付ける必要性がますます訴えられる結果となった。バヌアツも不満を漏らした。気候資金の新たな目標である新規合同数値目標(NCQG)や緩和緊急拡大作業計画(MWP)、適応に関する世界全体の目標(GGA)などの重要な議題において進展が見られないことに深い懸念を表明し、COPがこれまで長い間続いてきたこと、今後はこれまで通りの対応では済まされないことを強調した。実際に、温室効果ガスの排出量や地球の平均気温は毎年記録を塗り替え続けている。ICJでの審理にますますの期待がかかることになった。

COP29での小島嶼国に関する協議の様子(写真:Commonwealth Secretariat / Flickr[CC BY-NC 2.0])
声の高まり
こうした声をICJへ持ち込み、各国の気候変動への義務と責任を明確にしようとする今回の試みは、南太平洋大学バヌアツキャンパスの国際環境法の教室から始まった。2019年、この教室に集まった27人の法学生たちが「実践学習」の一環として、気候変動に対処するための最も進歩的な法的手段としてあらゆる規模の国々に判例を作ることを目標に掲げた。しかし、学生たちは教室での学習にとどまらなかった。弁論趣意書を執筆してPIF各国に送付した。また、バヌアツの外務大臣にも直接持ち掛け、感銘を受けた外務大臣は政府レベルで動き出すことになった。そして2022年、バヌアツの主導の下PIFによりICJに勧告意見を求めることが公式に決定された。
ICJに勧告意見を要請するには、一定の手続きを踏まなくてはならない。ICJは国際連合憲章第96条に基づき、総会と安全保障理事会、または総会の許可を得たその他の機関及び専門機関からのみ勧告意見の要請を受け付けている。PIFは国連総会による要請という道を選び、国連加盟国からの支持を得るために動き出した。国連総会での採択を目指すにあたり18か国(※2)からなる中核グループが結成され、草案を審議・作成した。2023年3月の第77回国連総会では全会一致で決議が採択された。気候変動における国際法上の国家の義務について意見を述べるようICJに要請することが決定した。
公聴会にて
ICJに投げかけられた質問は2つ。「国家は、国際法上、現在および将来の世代のために、温室効果ガスの排出から気候システムや環境を保護していくためにどのような義務を負っているのか」、「これらの義務の下で、国家がその行為・不作為によって気候システムや環境に重大な損害を与えた場合、どのような法的結果が生じるのか」。特に2つ目の質問については、環境に重大な損害を与えてきた高所得国の負う小島嶼低所得国などの国家に対する責任を問うものである。

ICJでのバヌアツ代表の陳述の様子(写真:UN Photo/ICJ-CIJ/Frank van Beek [Fair use])
2024年12月2日から開始された公聴会では、主導したバヌアツの国土資源大臣ラルフ・レゲンバヌ氏が初期答弁を行った。バヌアツは他国が行った行為の被害者であるとし、気候変動に加担している温室効果ガスの高排出国から被害に対する補償を受ける権利があると主張した。気候変動は政治的、経済的、社会的、文化的側面を支える環境を変化させることで、国連憲章にある国の自決権を阻害していると述べた。多くの国や組織がおおむね同意を示した。また、南太平洋大学でこの運動を始めた学生のひとりも公聴会で陳述を行っている。
グレナダ、クック諸島など39の小島嶼国及び低平な沿岸低所得国をまとめる小島嶼国連合(AOSIS)も出席し、国際法は気候変動とその不平等な影響に対応するために進化させなければならないと主張した。また、技術的・再生的支援の提供とともに、気候変動の影響を受ける地域における「国家の存続」の原則を確認するよう求めた。海面上昇によって国家の陸地領土が物理的に変化したり、完全に浸水したりした場合にも国家の存在を維持するためである。
しかしながら、主要な温室効果ガス排出国の多くは新たな法的責任の設定に消極的な姿勢を示した。例えば、石油生産大国であるサウジアラビアは、既存の気候変動に関する国連条約が国家の義務についてすでに完璧な答えであると主張し、さらなる法的責任を定めることに反対した。総会決議案を起草した中核グループのメンバーであったドイツもパリ協定が国家の義務を定める決定的な条約であるとして、他国からの落胆の声を集めた。
さらなる法的責任に反対したのは、上の国々に加え、アメリカ、イギリス、オーストラリア、中国、南アフリカなどである。年間の二酸化炭素排出量が最も多い中国は、温室効果ガスの排出は、一般国際法上、国際的な不法行為には当たらないと述べた。第2の温室効果ガス排出国であるアメリカは、その責任を認めつつも、気候危機は国際協力によってのみ解決できるものであるとし、既存の条約に法的拘束力を持たせることには消極的であった。

オーストラリアの炭鉱の様子(写真:Adani Mining Australia / Wikimedia Commons[CC BY-SA 4.0])
期待と失望
今回のICJへの持ち込みは、様々な面で社会的意義を残すだろう。まず、環境への損害に対する義務・責任の法的効果を明確にしようとしたことは国際環境法における画期的な一歩として多くの国やNGOから高く評価されている。ICJにおいて過去最多の100以上の国や組織が意見陳述に参加したことは、世界の関心の高さを表している。それに加えて、「脆弱」とされる国々だけでなく欧州連合(EU)や石油輸出国機構(OPEC)などの国際機関からも陳述を受けた点も、前例のない瞬間だと評価されている理由である。またこれは、低所得国が構成するいわゆる「グローバルサウス」の国々よる多国間外交の成功例としても語られる。
審理は数か月を要し、ICJからの最終的な勧告意見は2025年中に出されると見られている。勧告意見とは、拘束力はもたないものの、法的な重みと権威を有する裁判所の決定として尊重されるものである。また、国際法の解釈と発展にも貢献するものである。今回の気候変動に関する勧告的意見は、今後の世界的な司法手続きに影響を与えたり、国内裁判で参照されたり、外交交渉を左右したりする可能がある。国連事務総長のアントニオ・グレーテス氏は、「より大胆で強力な気候変動対策を講じるのに役立つだろう」と述べている。
一方で、この議論は明確な対立構造を浮かび上がらせた。アフリカ・カリブ海・太平洋諸国機構(OACPS)の代表クリステル・プラット氏は、気候変動対策のための既存の枠組みを超えるべきではないと訴えた大国に「大きな失望」を表明した。新たな気候条約を作るだけでなく、国際法全体を見直す必要があると強調した。
世界中の人々の安全な未来が保証されるように、まずはICJの勧告意見を期待して待ちたい。
※1 ニウエは国として太平洋諸島フォーラム等の地域機構に参加しているが、国連加盟はしていない。
※2 アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、バングラデシュ、コスタリカ、ドイツ、リヒテンシュタイン、ミクロネシア連邦、モロッコ、モザンビーク、ニュージーランド、ポルトガル、ルーマニア、サモア、シエラレオネ、シンガポール、ウガンダ、ベトナムの18か国。
ライター:Kyoka Wada

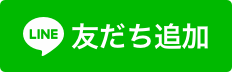









この大きな動きが、大学生の授業から始まったというところに胸が熱くなりました。次世代を生きる学生たちの切迫した思い、アカデミアが開かれた学問の場所であるべきことの意義を改めて考えることができました。
また、気候変動の原因を作り出してきた国々の責任逃れをしようとする態度には失望です。特に、「気候危機は国際協力で」という考え方は、現状の逼迫した状況を全く反映できてないと思いました。ICJが今後どのような判決を出すのか、高所得国の責任逃れをどのように阻止していくのか、一市民である私たちはどうすればいいのか、考えることがたくさんありそうです。
あまり知らない分野の話でしたが、とても興味深かったです!このような記事を書いていただきありがとうございます!