森林被覆率が50%を超える国、マレーシア。マレーシアにおける熱帯雨林の歴史はアマゾンやコンゴ盆地よりも古いと言われている。最も生物多様性に富んだ場所の一つといわれる熱帯雨林は、長い歴史の中で多くの恵みをもたらしてくれた場所である。一方、マレーシアでは、その森林への破壊が進んでいる。この記事では、マレーシアにおける森林破壊の背景や現状、そして近年どのような対策がとられているのかを探っていく。

ボルネオ島サワラク州でのパーム油プランテーションの様子(2012年)(写真:Edgar Vonk / Flickr [CC BY-NC-SA 2.0])
マレーシアについて
まずマレーシアの基本情報について理解したい。マレーシアはマレー半島に位置する西マレーシア(国土の約40%)と、ボルネオ島に位置する東マレーシア(国土の約60%)を国土とする。マレー半島、特にマラッカは、東アジアと中東・ヨーロッパなどをつなぐ交易の拠点であり、昔からさまざまな民族が居住地としてきた。やがてヨーロッパ諸国が進出し、1795年にイギリスがマラッカを占領した。イギリス統治時代には、労働力不足を補うために、中国やインド南部から人々がマレーシアに連行された。日本の占領などを経て、1957年にマレー半島部が独立、1963年にボルネオ島のサワラク・サバ地域がこれに加わった。1965年のシンガポールの独立分離を経て今のマレーシアとなった。
現在、マレー系住民とマレー語以外の言葉を話す先住民族(※1)から構成される「ブミプトラ」がマレーシアの人口の約63%を占める。ブミプトラとは「土地の子」を指す言葉で、マレーシアに昔から住んでいる人々を指す。また、中華系住民が人口の約20%、インド系住民が約6%を構成している。マレーシアがイギリスから独立して以来、経済的に優位に立ってきたのは主に中華系住民であり、この中華系優位の風潮に抗うために、マレーシア政府は、ブミプトラに対して、教育機関へのアクセスや公務員採用などにおいて優遇するといったブミプトラ政策を実施している。ブミプトラ政策は一部のマレー系住民に特権を与えた。しかし、同じブミプトラでもこの特権を享受できず、都市圏から離れた場所で、自給自足の生活を送り、マレーシアでも最低レベルの貧困や飢餓に苦しんでいる先住民族もいる。

次に、経済に注目をしてみよう。全体としては1960年から2017年まで国民総所得(GNI)が平均して年間6.9%という目覚ましい成長を遂げている。マレーシアの主要な輸出品は、集積回路、精製石油、天然ガス、パーム油、原油があげられ、特にマレーシアの主要な輸出品の一つであるパーム油は世界2位の輸出額を誇っている。パーム油の原料である、アブラヤシは世界の約90%が、マレーシアとインドネシアで栽培されている。
最後に政治体制について確認をする。マレーシアは連邦制立憲君主制国家である。13の州と3つの連邦直轄領からなる連邦制を通じて統治が行われる。そのうちの9つの州では基本的に世襲制で州の首長がおり、その首長らが通常5年ごとに交代で国の君主(スルタン)となる輪番制を採用している。基本的に象徴的な側面が大きいが、近年では、マレーシアで議会の状況が変わるに連れて、王室がより強い影響力を持つようになっている。議会では長年、統一マレー国民組織 (UMNO)が主導する国民戦線(BN)が権力を握り続けてきた。2018年の政権交代以降、マレーシア政治は新たな局面を迎えており、2022年11月の選挙では、野党勢力のアンワル・イブラヒム氏率いる希望同盟(PH)が議席を伸ばした。首相選出が難航したが、最終的には国王が助言をする形で与党連合が成立し、アンワル氏が首相となったという経緯がある。
マレーシアの森林の状況
マレーシアは昔から森林資源に恵まれてきた国である。そのため、森を開墾し、材木として木を輸出することで国を成長させてきた。1950年代のまだ材木への需要が少ない時には成熟した木を伐採し、将来のために若い木は残す、という方法で伐採がなされてきた。しかし、1970年代後半以降には木材への需要の増加に対応するために、より積極的に森林資源を管理・植林を行うようになった。詳しくは後述するが、プランテーション化をしたことで、木の成長に関係なく、木々が伐採されるようになった。さらに、木材だけでなくより利益を産むことのできるパーム油やゴムの木のプランテーションへと移行していった。
2020年時点で、マレーシア全体では1,910万ヘクタールの森林が存在している。マレーシアの国土の2割は、プランテーションに分類され、そのうちの58%は、パーム油農園である。その他にゴムの木のプランテーションが3.6%、材木用プランテーションが2.4%である。しかしその陰で2002年から2023年までで293万ヘクタールの原生林が失われている。
森林破壊は失われた森林の面積だけでは評価しきれない。森林伐採に付随する問題として、森林の「劣化」が挙げられる。特にボルネオ島の熱帯雨林は伐採によって大きな影響を受けている。森林資源を伐採する際にはブルドーザーなどの重機を使用する。これらは土壌、水路、森林構造にも影響を与えて、伐採されずに残った若い樹木にも40~70%の損害を与えてしまう。伐採する木を選別して、若い木を残そうとしても、残存樹木すらも影響を受けるのである。
森林が伐採され、木材やプランテーションに変化するなかで、マレーシアの生物多様性は失われつつある。例えば、2019年にはマレーシアで最後のスマトラサイが死亡している。また、1950年代には3,000頭ほど生息していたとされるマレートラも今では150頭ほどになっているうえ、政府のマレートラの保護政策も上手く働いていない。影響を受けているのは動物だけではなく、植物も同様であり、森林地帯で見られる種のうち、79.6%がアブラヤシのプランテーションでは確認できなかった。これは、プランテーションでは外来種の植物が多く生息しているからだとの見方がある。また、人間も森林伐採に影響を受けており、森林地帯で生活をしている先住民族が森林伐採に伴い移住を迫られている場合もある。
プランテーションとその背景
マレーシアの森林問題を理解するために欠かせないのがプランテーションであろう。単一作物を育てるプランテーションが森林に及ぼす影響は多大である。マレーシアで伝統的におこなわれられてきた、材木用の伐採と違い、プランテーション用に森林を開墾する場合には、まず全ての土地を伐採し、完全に不毛にするところからはじまる。その土地の自然のサイクルを完全に壊すことに等しい。このような商品作物栽培用のプランテーションの急激な拡大は、マレーシアの自然環境に甚大な影響を与えてきた。
しかし、パーム油の需要はとどまることを知らなかった。理由としてパーム油は、食品の原料、バイオ燃料、エンジンの潤滑油、化粧品のベースまで、さまざまな用途に使用されおり、汎用性が高いことが挙げられる。さらにバイオ燃料が注目を集めていることなどから、パーム油の価格は概ね上昇を続けている。プランテーションの拡大率と森林減少率が世界のパーム油価格と相関関係にあることが研究により明らかになっており、このような需要・商品価値の高まりが、プランテーションを拡大させているといえる。

ボルネオ島のサバ州で伐採された木々が運ばれていく様子(2009年)(写真:Alexey Yakovlev / Flickr [CC BY-SA 2.0])
プランテーションを「森林」に含めるかについては、分類方法によって異なるが、マレーシア政府は、プランテーションとして開発された土地も森林面積に含めることにより、人々の目を欺いてきた。マレーシアパーム油委員会(MPOC)は、他の商品作物よりも、パーム油のプランテーションは、森林に近く、森林として分類できると主張している。しかし、プランテーションは、単一の商品作物を大規模に育てることを意味しており、実際にマレーシアでは外来種の木も大量に植林されている。また、プランテーションの開発過程においても、自然林とは異なる性質を多く持っている。そのため、プランテーションを単なる森林と解するのは誤りであるとの指摘もある。
森林伐採会社と州政府、そして先住民と森林伐採との関係
マレーシアでは、国が定めた森林法が存在するが、マレーシアの連邦制度では、州政府が森林管理権や伐採への許可付与権など土地利用や環境保護に関するほとんどの規制の権限を握っている。しかし、州政府は、森林会社から税金と森林伐採の権利付与の際にかかるお金から収入を得ているため、環境保護への監視の目は緩くなる傾向があるとされている。また、地方自治体の役員や法執行官への賄賂も横行していると考えられ、政治的に腐敗をしているとも言える。さらに、許可を付与した場合にも、その森林がどのような使われ方をするのかについて企業が開示をする必要はないため、伐採後に別の企業がその土地を利用している場合には森林破壊の責任の所在が不明確になることが指摘されている。
このような腐敗や複雑な権利関係は先住民族との衝突を生み出している。ボルネオ島のサラワク州とサバ州では、イギリス植民地時代に成立した先住民族の慣習的土地権と慣習法を認める法律が今も施行されている。しかし、これらの法律は適切に施行されておらず、政府は先住民族コミュニティの権利と利益よりも、大規模な資源採掘と民間企業や政府機関によるプランテーションを優先している。完全に先住民を無視している行動だと先住民に関する出来事のための国際的作業グループ(IWGIA)は指摘する。
先住民族の土地は、名目上は森林法によっても保護されているが、この法律では先住民族の住居や公共スペースのための土地の権利、および国内消費のための伐採の権利は留保されている。そのため、先住民族のコミュニティがこの土地に関して何かの権利を主張するときには、まず初めに土地所有権の取得手続きをおこなう必要があり、この制度は非常に複雑になっている。先住民と森林伐採会社または州政府との間での対立は後を立たない。例えば、2021年にある森林伐採会社が字の読めない先住民族に「詐欺的」に「伐採・植林プロジェクトへの支援として住宅を受け入れる」という文書に署名をさせた疑惑が浮上している。

先住民族の家の様子(2008年)(写真:Nguyễn Thành Lam / Flickr [CC BY-NC-ND 2.0])
パーム油・木材はどこへ?
森林破壊の観点からも、また先住民への権利保護の観点からもマレーシアのプランテーションには問題が山積しているが、マレーシアのパーム油や木材には安定的に需要が存在する。2022年には、マレーシアのパーム油がインド(20%)、中国(6.9%)などに輸出されている。これらの国がパーム油の輸入を減らす可能性は低いと考えられる。パーム油の世界最大の消費国であるインド国内でも中国国内でもパーム油の生産計画がうまく進んでいないからだ。しばらくは環境への影響を考慮しないパーム油の輸入が行われるだろう。
また、マレーシアの木材ついては、2022年に日本(24.9%)、アメリカ(12.6%)、インド(8.1%)が輸出された。2017年には、東京オリンピックに際して計画された新国立競技場の建設現場において、マレーシアで違法伐採された木材が使用されていたことが問題になった。この時、サワラク州の住民は、当時の安倍晋三首相に「木材使用中止」を求める嘆願書を送付し、マレーシア内外の環境・人権NGOなどもこの動きを支援した。
マレーシアの森林保護
このような状況に対して、マレーシア政府は2007年に森林プランテーション開発計画を始めた。このプロジェクトでは、農家の人々に財政的なインセンティブを与えて、森林プランテーションを増やすことを目的としていた。森林保護区の樹林の伐採許可を州政府から付与した上で、新たな木を植林後に、15年間低利子の融資が受けられ、16年目から20年目にかけて返済を行う仕組みであった。この計画参加業者についての審査は詳しく行われなかったと見られており、森林保護区の森林を伐採したのち、植林を行わない悪徳事業者の存在もあるようだ。林業局のデータによると、2012年から2020年の間に、植林をされたのはわずか3分の1であった。多くの事業者は最初の伐採のときに得られる利益に飛びつきがちで、その先の長期的な利益については後回しになるようだ。

チェーンソーで丸太を切る作業員(マレーシア、クアンタン)(写真:Azami Adiputera / Shutterstock.com)
また、連邦議会は2022年に森林法の改定を可決した。この新しい法律では、森林保護区の森林の伐採許可付与の前に州政府が調査を行うことが義務付けられている。加えて森林産物の不法所持に対する罰金などもひきあげられている。これまでの森林法よりも厳罰化されているので、森林保護へのインセンティブになると見られている。しかし、前述の通り森林に関する権限の多くは州政府に帰属をして、連邦政府が行使できる権限は極めて少ない。マレーシアの制度では連邦政府が、改定をしても、各州の州議会で可決されなければ、法律はその州には適応されない。2024年4月時点で、改定された森林法を州議会で可決しているのはわずか2州だけであり、州政府と連邦政府の協力体制の強化が求められる。
連邦政府は国の代表として世界との調整役を担っている。欧州連合(EU)は2023年6月に森林破壊防止規則(EUDR)を発効し、パーム油、牛、コーヒー、木材などの森林破壊に寄与している可能性のある製品のEU圏への輸入と輸出の際に森林を破壊していないという証明が求められることとなった。これに対し、世界のパーム油輸出の約85%を占めるインドネシアとマレーシアの政府は当初EUDRについて厳しすぎると批判をしていた。その後、EU、マレーシア、インドネシアは共同で会議を重ね、EUDRへの対応を協議してきたが、同時に、マレーシア政府は公平な取引と小規模農家の保護のためにEUDRの適応を延期することを求めてきた。こうした求めに応じる形で、2024年10月にEUはEUDRの適応を1年遅らせることを発表した。延長された移行期間の中で、マレーシア政府がどのような対応を行うのか、今後が注目される。
しかし、EUDRが施行されたとしても、必ずしも森林破壊を止めるとは限らない。EUに代わる新たな消費者が現れる可能性があるからだ。実際に、2023年9月にマレーシアと中国の間で41億米ドル相当のパーム油に関連する投資契約の締結が発表され、マレーシアは今後中国へパーム油の輸出量を倍増させていく方針を明らかにしている。
マレーシアの森林破壊は凄まじいものであり、2000年から2012年には世界でも最も高い森林減少率を記録していた。しかし、近年は森林の減少率の鈍化も確認されている。自主的炭素市場(VCM)がマレーシアに導入されたことが、この結果をもたらした可能性が指摘されている。このシステムでは、温室効果ガスを排出する企業が温室効果ガスの排出権を購入し、そのお金で植林などの環境保全活動への投資がなされる仕組みだ。国の成長と森林保護をどのように両立するかについては複雑な問題であるが、マレーシアの森林の未来は必ずしも暗いものではない。
マレーシアで懸念されるその他の問題
マレーシアが抱える問題は森林伐採だけではない。大気汚染・プラスチック問題、廃棄物の処理など取り組まなければならない問題は山積している。自動車の使用の急激な増加に起因して、都市部の大気汚染指数は2020年に世界保健機関(WHO)のガイドラインの約2.6倍のPM10の排出量を記録している。そして、大気汚染が原因で毎年推定32,000人が死亡しているとの調査もある。

マレーシアの首都クアラルンプールでマスクをつける女性。このとき、インドネシアの森林火災により空気の状態がかなり悪くなっていた(2019年)(写真:Abdul Razak Latif / Shutterstock.com)
さらに、プラスチックごみの問題も深刻だ。マレーシアは年間で94万トンを超える不適切なプラスチック廃棄物を生み出し、世界で8番目に不適切なプラスチック廃棄物の発生国とされる。2018年長年プラスチックごみの集積場となっていた中国がプラスチックごみの輸入を禁止したことにより、マレーシアは、次なるプラスチックごみの集積場となった。しかし、マレーシアの廃棄物管理システムではこれらを処理しきれず、不適切な状態のまま海に流れ、海洋汚染に繋がっている。
また、世界で起きる気候変動はマレーシアにも影響を与えている。例えば海辺に生活拠点を持つ先住民は海面上昇の脅威により、家が水没するなどし、伝統的な生活を続けることは不可能になると考えられている。他にも、気候変動による不安定な天候や気候変動に伴う漁獲量の減少により、すでに家族代々続いてきた漁師の職を離れる人も出てきている。
マレーシア政府はこのような環境問題に関して、国家エネルギー移行計画を発表し、対策に乗り出した。ここでは2005年比で45%の温室効果ガスの排出量削減、2050年までに実質ゼロ達成を目指している。
これまで述べてきたように、森林伐採や大気汚染、プラスチック問題など、マレーシアを取り巻く環境問題は多く存在している。しかし、マレーシア政府が環境への危機感を持っていることも確かである。マレーシアの環境保護への歩みはまだまだ始まったばかりである。今後の動向が注目される。
※1 マレーシアにおける先住民族の解釈は様々存在する。ここでは、1954年の先住民法の「先住民族の言語を話し、習慣的に先住民族の生活様式や習慣に従っている人」という定義に従う。また、マレー系住民は「先住民族」には含まれない。IWGIAによると、マレーシアの先住民族は国民人口の約13.8%を占めるとされている。マレー半島の先住民族はオラン・アシル、サワラク州の先住民族はオラン・ウル、そしてサバ州の先住民族はアナク・ヌグリと総称される。
ライター:Ito Risa
グラフィック:Mayuko Hanafusa

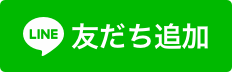









0 Comments