GNVはこれまで日本のメディアの国際報道でどのような事柄がニュースになるのかという点において、さまざまな調査を重ねてきた。明らかになってきた国際報道の傾向の一つに、G7サミット(首脳会議※1)などで議題となった事象について報道量が増えることがあるというものがある。2023年に「グローバル・サウス」がG7の首脳会議のテーマのひとつに選出され、突如として日本のニュースの中で使われるようになったことがその一例だ。
これまでのGNVの調査が明らかにしてきているように、日本のメディアは高所得国、そして権威を持つアクターの動向を報じる傾向があるため、G7で議題に上がったテーマはメディアの興味を引きつけやすいのかもしれない。今回は、「G7で取り扱われた議題は、報道になりやすいのではないか」という疑問から調査を行った。

2021年に開催されたG7でメディアに向けて声明発表をするイギリスのリシ・スナク首相(当時)(写真:HMTreasury / Flickr [CC BY-NC-ND 2.0])
G7の議題になった事象はニュースになる?
冒頭に挙げたグローバル・サウス報道の事例は、1969年に登場した「グローバル・サウス」という用語が日本のメディアではほとんど取り上げられてこなかったにも関わらず、2023年の日本の岸田文雄首相(当時)が広島で開催されたG7に合わせて「グローバル・サウス」という言葉を使うようになったのに呼応するようにメディアも使い始めたというものだ。
「グローバル・サウス」という言葉の使用が増えるに従って、グローバル・サウスの国々への関心が増えたり、課題が報じられるようになったのであれば、それは世界をより包括的に報じる第一歩となったことだろう。しかし、GNVの調査で明らかになったのは、グローバル・サウスという用語の使用が増えているにも関わらずそこで語られている多くは、ロシア・ウクライナ戦争などの状況を報じたものであり、グローバル・サウス諸国の状況を直接的に報じるものではなかったということだ。さらに、2023年5月に開催されたG7広島サミットと時を同じくして紙面登場のピークを迎えた「グローバル・サウス」は、サミットの閉幕とともに紙面で見ることも減っていった。
グローバル・サウス報道とよく似た傾向を示すのが、プラスチックごみに関する報道だ。プラスチック問題自体は近年始まったものではない。日本国内では1960年代から1970年代にかけて、プラスチックが公害を引き起こす原因の一つとして指摘されている。また、1980年代以降は、資源ごみの質の向上という観点からゴミの分別が全国各地で推進されるようになり、プラスチックのリサイクルが一般的な概念として広がって行った。また、より近年の国際的な動向として、ヨーロッパやアメリカで排出されたプラスチックごみを資源として輸入していた中国が、2017年にプラスチックごみの輸入に規制をかけるようになったことは国際的にも大きな注目を浴びた。
一方で、日本の主要3紙(※朝日新聞、毎日新聞、読売新聞)のプラスチック問題の国際報道量を見てみると、2017年までほとんど報道されてこなかったのが、2018年に急激に増え、2019年にピークを迎え、2020年以降はまた数を減らしている。2018年6月にカナダ・シャルルボアで開催されたG7サミットにおいて海洋プラスチック問題が大きなテーマとなり、日本とアメリカを除くイギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダの5カ国とEUが自国のプラスチック規制を強化することを示した「海洋プラスチック憲章」に署名した。過去のGNVの調査は、サミットの前後でのプラスチックごみに関連する記事の文字数の比較から、G7が大きなターニングポイントになっていたと指摘している。
その翌年、2019年には大阪で開かれたG20(金融世界経済に関する首脳会合)サミットにおいて、「2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減することを目指す『大阪ブルー・オーシャン・ビジョン』」が採択された。2019年のプラスチックごみ報道45件のうち、「G20」が見出しに含まれるものは3紙合わせて12件だった。また、G20が開かれた6月のプラスチックごみ関連の報道を文字数で見ると19,899文字であり、同年の6月以外の月のプラスチックごみ報道の文字数合計である23,090文字に迫る勢いだ。このことからも、G20の開幕とそこでのプラスチックごみについての議論と報道量が無関係であるとは言えないだろう。
パリ協定とG7の事例
上述の2つの事例ではG7やG20で議題になったり、議論に登った事象で同時期に報道の注目を集めたものを見てきた。ここから浮かび上がる一つの可能性が、G7で取り扱われた議題であれば、報道の注目を集めるのではないか、ということだ。そこで、G7で取り扱われたいくつかの事例に絞って、主要3紙の報道量(記事数)のピークを2015年から2023年の期間で追いかけた(※2)。するとG7で議題が取り上げられた時期と報道量が最も多かった時期は、必ずしも一致するわけではないということが判明した。
G7で議題に登ったにも関わらず、報道の注目時期が大きくずれている事象の一つがパリ協定だ。パリ協定とは、2015年12月の国連気候変動会議(COP21)で196の締約国によって採択された気候変動に関する国際条約である。パリ協定は「世界の平均気温の上昇を産業革命以前の水準より2℃をはるかに下回る水準に抑える 」、「気温の上昇を産業革命以前の水準より1.5℃に抑える 」ことを実現するための目標を掲げている。2015年、フランス・エルマウで開催されたG7サミットにおいて、同年12月にフランス・パリで開催が予定されていたCOP21での気候変動に関する枠組みの重要性について「G7エルマウ・サミット首脳宣言」内ですでに記述されている。しかし、2015年のG7が開催された段階で「パリ協定」という言葉はまだ使われるようになっていなかった。そのため、2015年の報道に関しては、G7の影響はないと考えられるものの、2015年のパリ協定に関する報道は18記事(22,873文字)であった。196カ国という多くの国の支持を受けて採択されたという実感は報道量からは伝わりにくくも感じるが、採択が行われたのが12月であったということから報道される期間自体が短かったことも報道量の少なさに影響しているのかもしれない。

2015年に開催されたCOP21でスピーチするブラジルのディルマ・ルセフ大統領(当時)(写真:Agência Brasil / Wikimedia Commons [CC BY 3.0 br])
続く2016年には94記事(72,647文字)、2017年には102記事(86,143文字)と着実に記事数、文字数ともに大きく増えていくため、2015年12月の採択から徐々にメディアの関心が高まっていったようにも捉えられる。
2016年の記事分布を詳しく見てみると94記事のうち、9月に20記事、10月に22記事、11月に35記事とパリ協定が発効した11月に向けて徐々に記事数が増えていく。記事の見出しに着目すると、メディアの注目はパリ協定自体ではないようだということがわかる。というのも、2016年の1年間で見出しにパリ協定と「米(文脈上アメリカを指している)」の両方を見出しに含む記事が20記事(22,272文字)もある。また、パリ協定と「トランプ」両方を見出しに含む記事も11記事(11,375文字)ある。2016年11月はアメリカの大統領選挙が行われた年でもあり、ここでトランプ候補者(のちの大統領)によるパリ協定からの脱退の発表がメディアの大きな注目を集めていたと考えられる。この傾向は2017年にはさらに顕著に表れている。2017年にパリ協定を見出しに含む102記事のうち半分以上の59記事(58,326)に「米」という言葉が含まれていた。また、「トランプ」氏の名前も11記事(6,722文字)の見出しに上がっていた。
一方で、2022年のドイツ・エルマウで開催されたG7の成果文章「G7首脳コミュニケ」内では「気候・エネルギー」という項目が設けられ、パリ協定と関連する記述があるにも関わらず、報道量は1記事(589文字)だ。また、2023年の日本・広島で開催されたG7サミットにおいても「G7広島首脳コミュニケ」という中心的な成果文章内で10回パリ協定という言葉が登場しているが、調査対象になった記事のうち2023年にパリ協定を見出しに含む記事はなかった。つまりパリ協定に関するメディアの集中的な注目は「アメリカ」の「トランプ氏」という一人の人物の発言によってもたらされたようだ。
もちろん、アメリカという経済的に大きな影響力を持つ国がパリ協定を脱退すれば、その影響は大きいだろう。しかしパリ協定に賛同した国は、アメリカを除いたとしても195カ国もあるのだ。また、あえて日本の報道機関という視点を強調するのであれば、日本も署名しコミットメントを表明しているため、パリ協定自体が重要なテーマであるとも言える。パリ協定という野心的な目標の本質について知り、実現に向けた世界の動きを知るという意味では、アメリカ以外の195カ国の取り組みの状況やパリ協定が必要とされるに至った気候変動の現状について市民が知ることも重要だろう。
債務問題報道とG7の事例
新型コロナウイルスが全世界で影響を及ぼすようになる以前から、経済成長が停滞傾向にあった中・低所得国では国民総所得に対する対外債務比率が上昇傾向にあった。そのような中で2020年前半に始まったパンデミックは各国の社会、経済に大きな打撃を与え、すでに債務問題を抱えていた中・低所得諸国にも深刻な影響を及ぼした。2021年にイギリス・コーンウォールで開催されたG7では、低所得の債務問題が議論に上がっている。この年のG7では、新型コロナウイルスへの対応として低所得国で2,000億米ドル、低所得国と高所得国の格差解消のために2,500億米ドルの予算が必要になるという国際金融基金(IMF)の試算を受けて、「債務支払猶予イニシアティブ後の債務措置に係る共通枠組(DSSI)」の再確認が行われた。DSSIは低所得国の公的債務の支払いを一時的に猶予する措置であり、2021年末のDSSI期間終了までに50カ国の129億米ドルの支払いが猶予されたという。

コーンウォールで開催されたG7での招待国首脳集合写真(写真:首相官邸ホームページ / Wikimedia Commons [CC BY 4.0])
しかし、2015年から2023年の3紙の報道で「債務」をキーワードに含む見出しを見てみると、最も記事数が多かったのは2023年の82記事(69,047文字)であった。G7で低所得国への債務支払い猶予が確認された2021年に債務をキーワードに含んでいた記事は40記事(24,556文字)であったことをみると、2023年の記事数はおよそ倍、文字数に至っては2.5倍以上だ。2021年の債務報道を見てみると、債務に加えて「米(文脈上アメリカを指している)」を含む記事が15記事(6,932文字)あり、この時期にアメリカ国内で問題となっていた債務上限の引き上げに関するものであることがわかった。また、16記事(12,446)には「中(文脈上、中国を指している)」の文字があり、同国の不動産会社である恒大の経営悪化や債務不履行を報じたものや中国による対外債務の貸付に関する記事が見られた。
2023年の債務に関する記事の見出しを見てみるとここでも「米」の文字が目立ち、記事数にして51記事(42,016文字)だ。2023年、アメリカでは政府の借金上限額である、債務上限額の引き上げをめぐり議論がなされていた。2023年の債務と米(アメリカ)を見出しに含む記事の多くが、アメリカ国内の状況を報じたものである。つまりG7で取り上げられた数多くの低所得国の債務問題よりも、アメリカ1国内の債務問題の方が大きな注目を集めているのだ。ここでも日本のメディアが報じる国際報道での、アメリカの動向への注目の高さが表れている。
潜在能力を発揮できない国際報道?
今回の調査で明らかになったのは、G7のような高所得国の集まりの国際会議で議論された内容も、必ずしもメディアの注目を集めるわけではないという点だ。もちろん冒頭に挙げたように、G7サミットをきっかけとして日本の報道機関の注目が集まることもある。しかし、複数の課題が議論されるG7サミットでは、全ての議題が報道の注目対象になるわけではない。むしろ今回の事例では、国際報道におけるアメリカの影響力の大きさを再確認する結果となった。すなわち、G7の議論に上がった課題であってもG7の文脈では報道には取り上げられず、アメリカというレンズを通して語られるケースがあることがわかった。GNVではこれまでも日本のメディアとアメリカの関係性について分析してきており、今回の調査結果もこれまでの調査結果に新たな事例を付け加える形になった。
政治・経済的に日本社会に大きな影響力を及ぼすアメリカの動向は、日本のメディアにとっても報道する価値があるという判断に繋がりやすいのかもしれない。しかし、日本に影響を及ぼしている国はアメリカだけではない。また、パリ協定などその背景に気候変動のような国境とは関係なく広がる課題があれば、アメリカの動向を見ているだけでは読者に世界を包括的に伝えることが難しくなるだけでなく課題の理解も進まない。
低所得国の債務問題のように、読者の生活と直接的には関係していないように見える課題でも、報道によって関心が醸成され課題解決を目指す何らかのアクションにつながる可能性もある。世界の課題を映し出すことで、現状の仕組みや構造を変え、世界をより良い方向に持っていこうとする人々の原動力となる潜在力が国際報道にはあるが、アメリカばかりを追いかけていては、その力を発揮することも難しいだろう。
※1 首脳会議という用語は外務省の用いるG7の日本語訳としてここでは使用しているが、参加しているのは必ずしも各国首脳のみではない。また、主要国首脳会議という用語も一般的に使われているが、何をもって「主要」とするのかについては議論の余地がある。例えば、世界人口という視点でみればG7諸国の人口合計は世界人口の10%未満である。
※2今回の調査は、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞の3紙の全国版の朝刊を用いて、該当するキーワードを見出しに含む記事数と文字数の2015年から2023年の変化を見た。なお、文字数は該当キーワードを見出しに含む記事の文字数の合計である。
ライター:Azusa Iwane
グラフィック:Virgil Hawkins

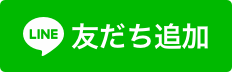









0 Comments